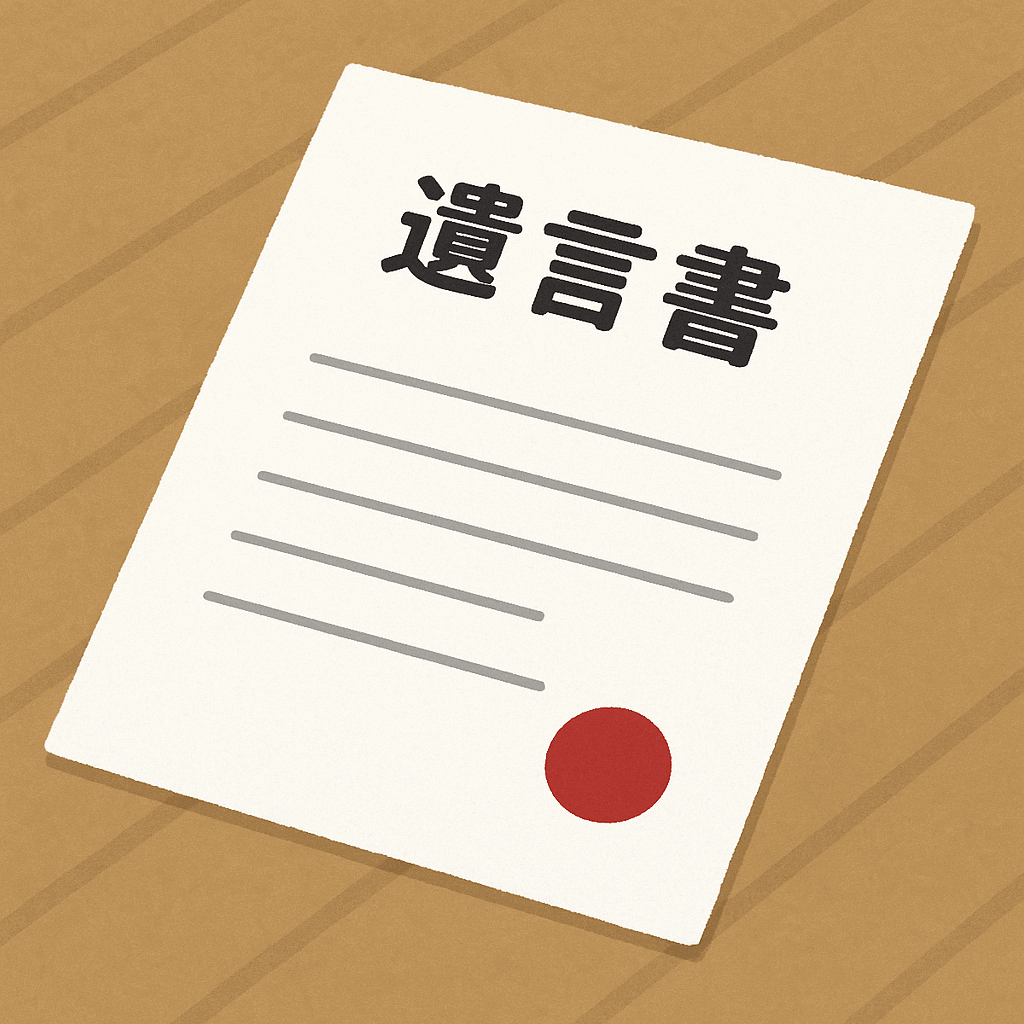大切なご家族がもめないために|遺言書の基本と書くべきケースとは?
この記事の内容は動画でも解説しています。あわせてご覧ください。
「遺言書って本当に必要なの?」「まだ元気なのに、書く意味あるの?」
こういったご質問を日々いただきます。
実際、遺言書がないままご相続が発生してしまうと、ご家族が大きな負担を抱えるケースも少なくありません。
今回は、司法書士の立場から
- 遺言書がないとどうなるのか
- 遺言書があることで何が変わるのか
- 書く上での注意点
- 特に書いておくべき人の特徴
など、遺言に関する基本をわかりやすく解説します。
遺言書がないと、相続人全員の話し合いが必要になります
遺言書がない場合、法律で定められた相続人(法定相続人)が、法律の割合(法定相続分)に基づいて遺産を相続することになります。
ただし、実際には「誰がどの財産を受け取るのか?」については、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をして決めなければなりません。
この話し合い、すんなり進むとは限りません。
- 連絡が取れない相続人がいる
- 意見がまとまらない
- 感情的な対立がある
こうした理由で、相続手続きが何ヶ月・何年とストップしてしまうこともあるのです。
相続手続きの基本的な流れ
ご相続が発生すると、次のような手続きを踏んでいきます:
- 相続人の確定(戸籍の調査)
- 財産の調査(預貯金・不動産・有価証券など)
- 遺産分割協議
- 名義変更や解約などの手続き
しかし、現場ではこれがスムーズに進まないケースも多くあります。
思わぬ落とし穴も…
実務上、次のようなトラブルに直面することもあります。
- 思いがけない相続人が見つかる※甥姪が相続人になるケースでは、祖父母の婚姻歴について把握していない例も多く、意外とよくあります。
- 故人の財産の所在が分からない
- 認知症・未成年・連絡が取れない相続人がいる→ 後見人や特別代理人の申立てが必要
- 分け方を巡ってトラブルが起き、協議がまとまらない
これらすべて、遺言書がないことで、ご家族が抱える負担です。
あらかじめ「こうしたことが起こるかもしれない」と知っておくだけでも、判断は大きく変わってくるはずです。
遺言書があると、何が変わる?
- 財産を「誰に」「どれだけ」遺すかを明確にできる
- 財産の所在を記載しておけば、相続人の負担が大幅に軽減
- 相続人同士の話し合いが不要に
- 手続きがスムーズに進む
遺言書は「ご自身の想い」と「手続きのしやすさ」の両方を残されたご家族に遺す、大切な手段です。
遺言を書くときの注意点
遺言には法律上のルールがあり、守られていないと無効になるおそれがあります。
たとえば自筆証書遺言の場合は:
- 全文を自分で書く
- 日付を入れる
- 署名・押印をする
また、認知症などで判断能力が低下してしまうと、遺言自体が無効になることもあります。
加えて、内容があいまいだったり、法的に問題があるような表現になっていると、逆にトラブルの元になることも。
だからこそ、専門家のサポートを受けながら進めるのがおすすめです。
特に遺言書を遺しておくべきケース
- 特定の相続人に多く遺したい方(例:長男に自宅を遺したい)
- 相続人同士の関係がよくない/揉める可能性がある
- 配偶者はいるが、子供・孫がいない場合(義兄弟との協議が必要)
- 内縁の配偶者やお世話になった方に財産を渡したい
- 認知症・未成年・連絡の取れない相続人がいる
- 事業の後継者に株式などを確実に引き継がせたい
ひとつでも該当する方は、できるだけ早めに遺言書の準備をご検討ください。
どこから始めればいいかわからない方へ
司法書士森成事務所では、遺言に関するご相談を初回無料で承っております。
ご依頼いただいた場合には:
- ご希望内容のヒアリング
- 法的リスクを踏まえたアドバイス
- 遺言書案の作成
- 必要書類の収集サポート
- 公正証書遺言の作成時には、公証役場との事前調整と証人としての同席
ご相談はいつでもお気軽にどうぞ
ご家族が困らないように、今のうちに準備を進めておくことがとても大切です。
司法書士が丁寧にお話をうかがいながら、あなたに合った形の遺言書をご提案いたします。
📩 ご相談は初回無料です。
具体的にどんな流れで遺言書を作成するのか知りたい方は、
下記のページでステップごとに詳しくご紹介しています。
📞 お電話でのご予約も受付中:047-712-5713
(受付時間:平日9:00〜18:00)