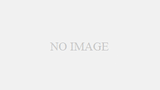遺言者より先に相続人や受遺者が亡くなったら?
〜予備的遺言による備え〜
遺言書作成のご相談にのる中で、ご相談者様からよく聞かれることがあります。
「財産を渡したい相手が自分より先に亡くなったら、どうなりますか?」
たとえば、
「自宅の土地・建物は妻に相続させる」
と遺言に書いていても、もしその奥様が遺言者より先に亡くなってしまったら…。
この自宅の土地・建物を奥様に相続させるという部分の遺言は効力を失ってしまいます。
その結果、自宅の土地・建物については、遺産分割協議によって、誰が相続するかを相続人全員で話し合って決めなければならなくなります。
つまり、遺言者が思い描いたとおりに財産を渡せないリスクが生じるのです。
このような事態を防ぐために有効なのが、予備的遺言(補充遺言)です。
予備的遺言とは?
予備的遺言とは、
「最初に指定した相続人や受遺者(遺贈によって財産を受け取る人)が遺言者より先に、または同時に亡くなった場合に備えて、次に誰に渡すかも決めておく」
という遺言の書き方です。
たいていの場合、「第一次的には〇〇に渡したいけど、その人がもし自分より先に亡くなっていた場合には、第二次的にはその財産は□□に渡したい」というような自分の中での構想があるものです。
これを実現するのが予備的遺言です。
たとえば、次のように記載します。
【予備的遺言の例】
第1条 遺言者は、遺言者の妻A(生年月日○年○月○日)に、遺言者の所有する次の不動産を相続させる。
(不動産の表示 省略)
第2条 妻Aが遺言者より以前に死亡していたときには、前項の不動産を遺言者の長男B(生年月日○年○月○日)に相続させる。
このように、万一のケースに備えて「次の指定」まで書いておくことで、遺言が無効になるリスクを抑えることができるのです。
予備的遺言をしておくメリット
- 遺言が無効になるリスクを減らせる
第一順位の相続人や受遺者が先に亡くなった場合でも、次の受取人が指定されているため、遺言の内容が生きる。 - 無用な相続トラブルを防げる
予備的遺言がないケースで相続人や受遺者が遺言者より先に、または遺言者と同時にお亡くなりになっていた場合、指定された財産については「遺言がなかったもの」として扱われ、相続人全員で遺産分割協議をして誰が相続するのかを決める必要が出てきます。
これにより、話し合いが難航したり、思いもよらぬ人に財産が渡ってしまったりするリスクもあります。
予備的遺言をしておけば、こうしたトラブルを未然に防ぐことができます。 - 遺言者の想いをより確実に実現できる
どんな状況になっても、自分の財産を「この人に渡したい」という想いを、最大限尊重できるようになります。
まとめ 〜遺言にもリスク管理を〜
今回は予備的遺言についてご紹介しました。
受遺者や相続人が自分より先に亡くなった場合のリスクに備えることも、とても大切です。
「もしもの備え」として、予備的遺言を活用し、
あなたの大切な財産を、想いどおりに届けられる形を整えておきましょう!
既に遺言書を作成されている方も、定期的に読み返してみて、今の想いが実現される内容になっているかな?と確かめてみることもとっても大切です。
弊所では、新たな遺言書作成のサポートはもちろんのこと、既に作成した遺言書の一部について「予備的遺言を追加したい」、「一部修正したい」などのご相談も承っております。
あわせて読みたい
📺 遺言や相続についてもっと知りたい方は、動画でもご覧いただけます。