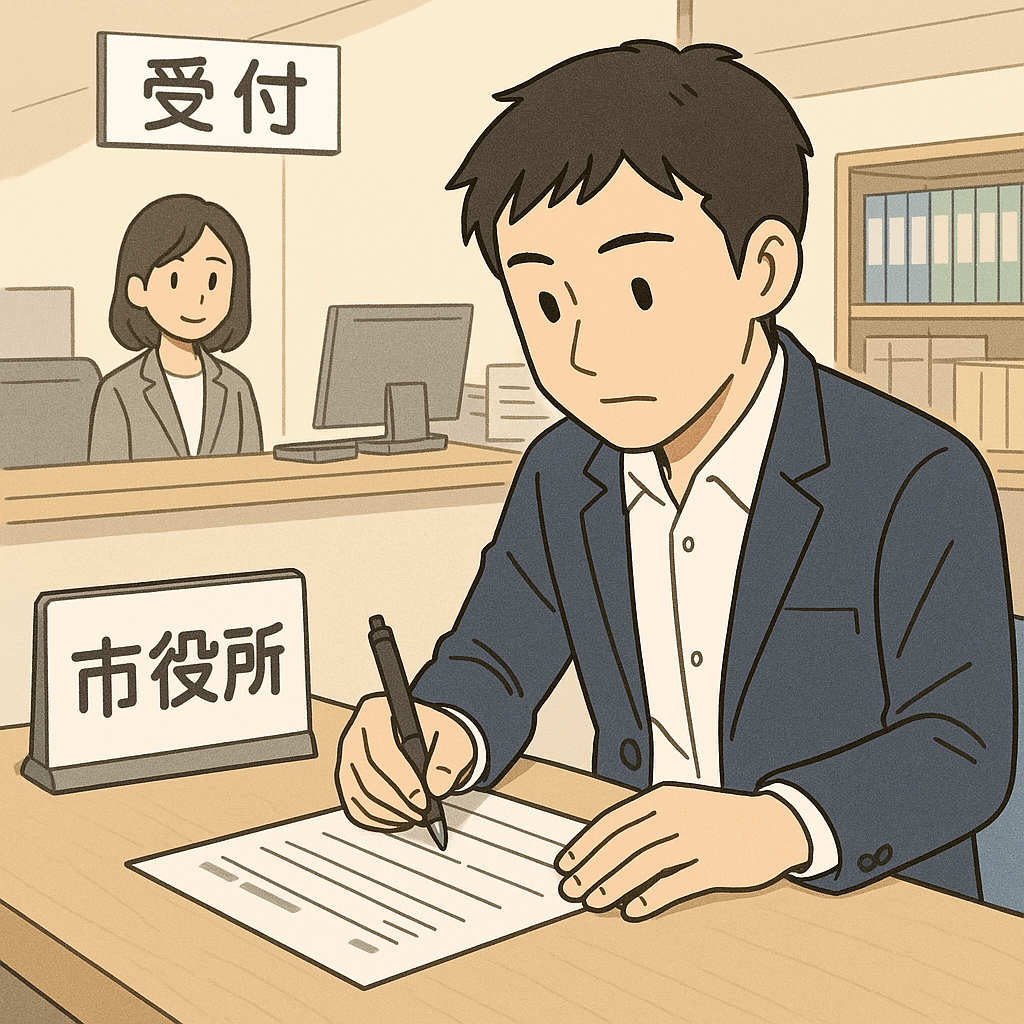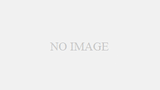第1章:ご相続発生後すぐにやるべき浦安市での手続きまとめ
ご家族が亡くなられたあとは、深い悲しみや戸惑いの中にいらっしゃることと思います。
そんな中でも、いくつかの手続きには期限が決まっているため、なるべく早めに動かなければならない場面も出てきます。
この章では、浦安市で必要となる「ご相続発生後すぐの手続き」について、できるだけわかりやすく整理しました。
まずは、期限があるものから順に対応していくことをおすすめします。
【チェックリスト】ご相続発生後すぐに必要な主な手続き(浦安市版)
| 手続き名 | 内容 | 期限 | 担当窓口 | 必要書類など |
|---|---|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 死亡診断書とあわせて提出。火葬許可証の発行にも必要。 | 死亡から7日以内 | 市民課(市役所1階) TEL:047-712-6267 | 死亡診断書(兼死亡届)、届出人の印鑑 |
| 火葬許可申請 | 火葬するには許可証が必要。死亡届と同時に提出。 | 同上 | 同上 | 上記と同じ(死亡診断書) |
| 健康保険証の返納 | 故人の保険証を返却(国保・後期高齢者)。死亡を証する書面も必要。 | 死亡から14日以内 | 国保年金課 TEL:047-712-6829 | 保険証、死亡届など死亡を証する書面、届出人の本人確認書類、印鑑 |
| 葬祭費の申請 | 国民健康保険の加入者に対して、葬祭費5万円を支給(浦安市)。 | 葬儀の翌日から2年以内 | 同上 | 保険証、印鑑、振込先口座情報、葬儀の領収書・会葬礼状など(葬祭事実および葬祭執行者の確認資料) |
| 高額療養費の還付申請 | 生前に医療費が高額だった場合に、自己負担分の一部を還付。 | 診療月の翌月1日から2年以内 | 同上 | 被保険者証、医療機関の領収書、印鑑、振込先口座の通帳、戸籍謄本など |
| 世帯主変更届 | 故人が世帯主だった場合に、新たな世帯主を届け出(同一世帯に15歳以上の方が2名以上いる場合)。 | 死亡から14日以内 | 市民課(市役所1階) TEL:047-712-6267 | 新しい世帯主の本人確認書類、印鑑など |
| 年金受給停止・遺族年金の手続き | 故人の年金の停止と、遺族年金等の申請。 | できるだけ早めに | 市川年金事務所(TEL:047-704-1177) | 年金手帳、死亡の記載がある戸籍謄本、遺族の本人確認書類、振込先通帳など |
【Point】見落としがちな注意点
- 印鑑登録証やマイナンバーカードは、浦安市では返納不要とされています。破棄しても差し支えありませんが、相続手続きで必要になることもあるため、すべての手続きが終わるまでは保管しておくのが安心です。
- 葬祭費の申請は、申請しないと支給されません。忘れずに手続きを行いましょう。
- 年金受給停止の手続きが遅れると、故人の口座に年金が振り込まれてしまうことがあります。その場合、後から返金手続きが必要になるため、早めに年金事務所へ連絡することをおすすめします。
- 会社員など、国民健康保険以外の健康保険に加入していた場合は、勤務先が脱退手続きを行います。保険証は速やかに勤務先へ返却しましょう。
また、扶養に入っていたご家族は国保への加入や他の家族の扶養に入るなど、切替手続きも必要です。
【一言アドバイス】
「何からやればいいの…?」と感じてしまうのは当然です。
まずはこの章の表を上から順にチェックしていくことから始めてみてください。
できる範囲で、無理のないペースで。
ご家族を亡くされた悲しみの中でも、手続きが少しでもスムーズに進むよう、心から願っています。
第2章:浦安市役所で行う主な手続き
ご相続発生後に必要となる手続きの多くは、浦安市役所で行います。
それぞれの手続きには提出先や持ち物が異なるため、事前に整理してから来庁することが大切です。
この章では、浦安市役所で対応できる主な手続きと、担当窓口・必要書類を一覧にまとめました。
【一覧表】浦安市役所でできる主な手続きと窓口情報
| 手続き名 | 担当課(直通電話) | フロア | 必要書類・注意点 |
|---|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 市民課(047-712-6267) | 1階 | 死亡診断書(死亡届と一体)、届出人の印鑑 |
| 火葬許可申請 | 同上 | 1階 | 上記と同時提出(死亡届と兼用) |
| 世帯主変更届 ※同一世帯に15歳以上の方が2名以上いる場合に必要 | 同上 | 1階 | 新世帯主の本人確認書類、印鑑 |
| 健康保険証の返納(国保・後期高齢者) | 国保年金課(047-712-6829) | 2階 | 健康保険証、死亡届など死亡を証する書類、届出人の本人確認書類、印鑑 |
| 葬祭費の申請 | 同上 | 2階 | 国民健康保険証、印鑑、葬儀を行った事実と葬祭執行者が確認できるもの(葬祭費用の領収書・会葬礼状など)、葬祭を行った方の振込口座がわかるもの |
| 高額療養費の還付申請 | 同上 | 2階 | 被保険者証、医療機関の領収書、戸籍謄本、通帳、印鑑など |
| 介護保険証の返納 | 介護保険課(047-712-6403) | 3階 | 被保険者証、介護保険負担割合証(該当者のみ)、申請者の本人確認書類、振込口座、印鑑 |
| 障がい者手帳などの返却 | 障がい福祉課(047-712-6394) | 3階 | 故人の各種手帳等、印鑑など |
| 固定資産税に関する届出(相続代表者指定届・納税管理人変更届) | 固定資産税課(047-712-6065) | 2階 | 本人確認書類、被相続人との関係がわかる書類(戸籍・住民票等)、納税通知書、相続代表者指定届・納税管理人変更届の写しなど(申請内容に応じて) |
【市役所以外で行う主な手続き】
| 手続き内容 | 担当機関・窓口 |
|---|---|
| 年金受給停止・遺族年金の請求 | 市川年金事務所(日本年金機構)TEL:047-704-1177 |
| 相続登記(不動産の名義変更) | 管轄の法務局 |
| 相続税の申告・納付 | 所轄の税務署(例:市川税務署など) |
| 銀行・証券口座の名義変更 | 各金融機関の窓口 |
| 生命保険などの請求 | 加入していた保険会社など |
【一言アドバイス】
浦安市が配布している「おくやみハンドブック」には、こうした手続きを一覧で確認できる資料が掲載されています。
来庁前に必要な書類を整理しておくことで、一度の来庁で複数の手続きを済ませることも可能です。
平日に何度も足を運ばずに済むよう、電話での事前確認や必要書類のメモを取っておくことをおすすめします。
第3章:相続手続き全体の流れを把握しよう
ご相続発生後の市役所での手続きがひと段落すると、次に控えているのが「相続」の手続きです。
相続の手続きは、遺産の種類や関係者の状況によって内容が大きく変わりますが、全体像を把握しておくことで、慌てず優先順位をつけて進めることができます。
この章では、相続に関する主な流れをわかりやすく整理します。
【図解】相続手続きの全体像(目安時系列)
| 時期 | やること | 主な内容 |
|---|---|---|
| ご相続発生直後〜7日以内 | 死亡届の提出、火葬許可、葬儀など | 市役所での手続き(第1・2章) |
| 1週間〜1か月 | 初期対応・遺言書の確認・相続人調査 | 遺言書の有無確認/検認手続き/戸籍収集など |
| 1か月〜3か月 | 財産調査・相続放棄の検討 | 預貯金・不動産・保険・借金などの洗い出し/相続放棄は3か月以内に家庭裁判所へ |
| 3か月〜4か月 | 遺産分割協議の開始 | 相続人間で財産の分け方を協議・文書化(協議書作成) |
| 4か月以内 | 準確定申告(故人の所得税) | 会社員や個人事業主だった方などは税務署へ申告 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付(必要な場合) | 一定額を超える相続財産がある場合は税理士と相談 |
| 協議後すぐ | 名義変更、相続登記、預貯金の解約など | 不動産の相続登記、銀行口座の解約などを順次実行 |
【Point】生命保険の請求は早めにできる
生命保険については、遺産分割協議を待たずに請求できるケースが多くあります。
受取人が指定されていれば、相続財産とは別枠(みなし相続財産)として扱われ、死亡届や保険証券、受取人の本人確認書類などをそろえれば、比較的早期に支払われます。
ただし、いくつか注意点があります。
- 一般的に、死亡日から3年以内(かんぽ生命は5年以内)に請求しないと、保険金を受け取る権利が消滅してしまいます。
- 被相続人自身を受取人としている契約の場合、保険金は相続財産に含まれるため、遺産分割協議が終わるまで請求できません。
まずは保険証券を確認し、受取人が誰になっているかを把握しておくことが大切です。
【Point】相続放棄は「3か月以内」に家庭裁判所へ
相続人は、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。
万が一、借金の方が多いかもしれない…という場合は、「相続放棄」や「限定承認」などの手段も検討する必要があります。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」に、家庭裁判所で手続きを行わないといけません。
【Point】遺言書がある場合は勝手に開封しない!
遺言書が残されていた場合、それが「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」であれば、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
(※ただし、法務局の遺言書保管制度を利用して保管された自筆証書遺言は検認不要です)
勝手に開封してしまうと、相続人間のトラブルの原因になることもあります。
専門家に相談のうえ、適切な手続きを踏んで開封しましょう。
【一言アドバイス】
相続手続きは「期限のあるもの」と「急がなくてよいもの」が混在しています。
まずは、早めに対応が必要な手続き(放棄・税申告)を見逃さないようにしつつ、残されたご家族でじっくり話し合って進めていくことが大切です。
関連コラム
Youtube関連動画
第4章:不動産がある場合の相続登記手続き
相続財産に「不動産」が含まれている場合、必要になるのが「相続登記」です。
これは、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きで、2024年4月からは義務化されています。
この章では、相続登記の基本と、どのように進めていけばよいかを解説します。
【相続登記とは?】
相続登記とは、法務局に申請して、亡くなった方(被相続人)名義の不動産を、相続人名義に変更する手続きのことです。
土地や建物を相続した場合、これをしないと売却・建替・担保設定などができません。
【義務化のポイント】2024年4月スタート
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 対象 | 2024年4月以降に発生した相続だけでなく、過去の相続にも適用 |
| 期限 | 相続により不動産の所有権を取得したことを知った日(遺産分割で不動産を取得した場合は遺産分割の成立の日)から3年以内に登記申請が必要 |
| 罰則 | 正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料 |
【誰の名義にすればいい?】
相続人が複数いる場合、必ずしも「全員の共有」にしなければならないわけではありません。
以下のような流れで、不動産を誰が相続するかを決めます:
- 遺言書がある場合 → 遺言書の指定どおり
- 遺言書がない場合 → 相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産を相続する人を決める
【必要書類の一例】
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 被相続人と相続人全員の相続関係を証明するための戸籍一式 | 被相続人と相続人の親族関係によって必要な戸籍は異なるが、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式と、相続人全員の相続発生日後に取得した戸籍は必ず必要 |
| 被相続人の住民票の除票 | 本籍地入りのもの |
| 相続人全員の住民票 | 本籍地入りのもの |
| 相続人全員の印鑑登録証明書 | 期限はないが、現住所のもの |
| 遺産分割協議書 | 相続人全員が署名押印したもの。 |
| 課税明細書(または固定資産評価証明書) | 登録免許税の計算に使用。市役所または都税事務所で取得可能 |
【Point】団信付き住宅ローンがある場合は抵当権抹消も忘れずに
被相続人を債務者とする抵当権が不動産に設定されている場合、
団体信用生命保険(団信)に加入していた住宅ローンなら、返済義務は保険によって消滅するケースがほとんどです。
この場合、金融機関へ連絡することで、抵当権の抹消登記を進めるための書類を発行してもらえます。
相続登記とあわせて、抵当権抹消の手続きも忘れずに行いましょう。
【一言アドバイス】
不動産の相続登記は、戸籍や住民票の収集、相続関係の整理、遺産分割協議書、登記申請書の作成など、専門知識と煩雑な書類準備が必要な手続きです。
しかも、書類に不備や不足があると、法務局から補正を求められ、何度も足を運ぶことになりかねません。
そうした負担を避け、最初からスムーズに手続きを進めるためには、相続登記の専門家である司法書士に依頼するのが確実です。
また司法書士は、登記だけでなく、銀行口座の解約や証券の名義変更など、相続全体の流れを見渡して、手続きの交通整理役を担うこともできます。
「何から始めればいいか分からない」と感じたら、まずはご相談ください。
🎥 関連YouTube動画
📚 関連コラム
第5章:相続税がかかる場合の注意点
相続と聞いてまず「税金はかかるの?」と心配になる方も多いのではないでしょうか。
相続税の特例を使うことで相続財産額が圧縮され、結果として相続税の支払いが不要というケースも多いですが、特例を適用するには相続税申告をする必要があります。
浦安市に不動産をお持ちの方は、浦安市は土地の相続税評価額が高いので、かなりのケースで基礎控除額を超え、相続税申告が必要になります。
この章では、相続税の基本と、手続きの流れを簡潔にまとめます。
【Point】相続税がかかるのはこんなとき
| 判定基準 | 内容 |
|---|---|
| 基礎控除額を超える相続財産がある | 3,000万円 + 法定相続人の人数 × 600万円 を超えると課税対象 |
| 課税対象の財産 | 被相続人の有する一切の財産から債務葬儀費用を控除した金額(例:土地・建物・預貯金・有価証券・自動車・ゴルフ券・貴金属・その他財産・死亡保険金(みなし相続財産)・相続開始前7年以内の贈与財産など) ※死亡保険金には、法定相続人1人あたり500万円までの非課税枠があります。 |
| 控除や特例を適用できないケース | 小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減が使えない場合は負担が大きくなることも |
【期限】相続税の申告と納付は10か月以内!
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 申告期限 | 被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内 |
| 納付期限 | 申告期限と同じ(基本は現金一括納付) |
| 納税方法 | 原則は現金納付。延納や物納も可能だが、要件・審査あり |
【準確定申告とは?】相続税とは別に必要な手続き
被相続人に確定申告の必要な収入があった場合、
その年の1月1日からご相続発生日までの所得について、相続人が代わりに確定申告を行う必要があります。これを「準確定申告」といいます。
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 申告期限 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内 |
| 申告先 | 被相続人の死亡当時の住所地を管轄する税務署 |
| 申告方法 | 相続人全員の連名で申告(一定の条件の下、個別に申告することも可能) |
【Point】不動産評価は「小規模宅地等の特例」で大きく変わる
亡くなった方の自宅(土地)を相続する場合などは、
条件を満たせば土地評価額が最大80%減額される「小規模宅地等の特例」が使える可能性があります。
ただし、使えるかどうかの判定は細かい要件を確認する必要があるため、相続税専門の税理士に早めに相談することが重要です。
【一言アドバイス】
相続税は「対象者が少ないから関係ない」と思われがちですが、
相続財産に不動産がある場合は、思ったよりも評価額が高くなり、課税対象となるケースもあります。
「うちは大した財産がないし相続税はかからないから」と決めつけてしまっているご相談者様も多いのですが、
実際には明らかに申告が必要だったり、申告が必要かどうか微妙なケースもよくあります。
そのような場合には、当事務所から相続手続きに詳しい税理士をご紹介していますので、安心してご相談ください。
第6章:相続手続きを専門家に依頼するメリット
相続の手続きは、「戸籍を集めて、登記や銀行の名義を変えるだけ」と思われがちですが、実際は非常に多くの工程と専門知識が必要です。
ここでは、相続手続きを専門家に任せることでどんなメリットがあるのかを解説します。
【司法書士に依頼するメリット】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登記の専門家として確実・スムーズ | 相続登記の申請ミスや補正を防ぎ、最短での登記完了が可能です。 |
| 書類の収集から一括対応 | 戸籍・住民票・評価証明書などの収集も丸ごと任せられます。 |
| 金融機関の手続きにも対応 | 預貯金の解約・名義変更・株式口座の手続きなども代行できます。 |
| 他士業との連携が可能 | 税務に関しては相続専門の税理士、相続人間のトラブルに関しては相続専門の弁護士を紹介可能です。 |
【Point】「専門家に頼むほどでも…」が一番危ない
相続は一生に何度も経験するものではありません。
そのため、多くの方が「とりあえず自分でやってみよう」と進めてしまい、
途中で行き詰まってから慌てて相談に来られるケースが非常に多いです。
最初の段階で全体像を整理し、スムーズに進めるためにも、専門家のサポートを受ける価値は十分にあります。
【一言アドバイス】
当事務所では、相続登記に加え、預貯金の解約、証券口座の名義変更なども対応可能です。
さらに、ご要望があれば、二次相続の対策に関しての提案も行っております。
また、手続きを進める中で、相続税申告の必要な可能性があることが判明した場合は、相続に強い税理士のご紹介もさせていただきます。
「何から始めたらいいのかわからない」そんなときこそ、まずはご相談ください。
関連コラム
まとめ|「何から始めればいいかわからない」ときこそ、ご相談を
相続の手続きは、「期限」「必要書類」「判断の分かれ目」が多く、
ご自身で完結しようとすると、思った以上に時間と労力がかかることがあります。
特に浦安市で相続が発生した場合、地元ならではの不動産評価や行政手続きの特色があるため、
地域の実務に精通した専門家に早めに相談することが、トラブルや後悔を避けるポイントです。
初回相談は無料|浦安市の相続に詳しい司法書士が対応します
当事務所では、
- 書類収集によるご相続人調査
- 遺産分割協議書の作成
- 相続登記
- 法定相続情報の作成
だけでなく、
- 個別の預貯金や証券口座の解約手続き
- 遺産整理業務(財産調査および解約・払戻し・名義変更の手続き)
にも対応しております。
相続専門の税理士と太いパイプがあります!
相続人間に争いがない限り、司法書士と税理士へご依頼いただければ、相続手続きはほぼお任せいただくことができます。
【事務所案内】
司法書士森成事務所
代表司法書士:森成 翔(千葉司法書士会所属)
所在地:〒279-0002 千葉県浦安市北栄3-33-9-102
電話番号:047-712-5713
受付時間:平日9:30〜18:00(土日祝のご相談も可能な限り対応いたします)
対応地域:浦安市・市川市・江戸川区ほか周辺地域
【無料相談のご案内】
当事務所では、初回60分まで無料相談を実施しています。
「何から始めたらいいか分からない」という方も、お気軽にお問い合わせください。
✅ まずはお気軽にご相談ください
- ご相談は事前予約制です(お電話・メール・フォームより受付)
- オンライン相談(Zoom)にも対応可能です
- 平日夜や土曜のご相談も柔軟に対応いたします
お電話でのご予約も可能です(047-712-5713)
相続手続きに関する料金表ページ
相続手続きに不安がある方へ
ご相続発生後の手続きは、不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、戸籍収集・遺産分割協議書・預貯金の解約など多岐にわたります。
当事務所では、相続に特化した司法書士が一括対応。
初回相談は無料、オンライン・土日もご相談可能です。お気軽にご連絡ください。