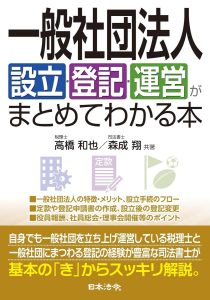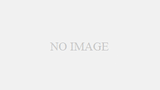「一般社団法人って、どんな人が作ってるの?」
そう聞かれることがよくあります。
社会貢献をしている団体?それとも専門的な資格を持った人たち?
実はそのイメージ、少しだけ偏っているかもしれません。
実際には、地域で活動している任意団体の方、会社とは別に社会的な取り組みを始めたい経営者、福祉や教育分野で行政と関わる事業を始めたい人など、さまざまな立場の方が、一般社団法人を設立しています。
この記事では、そうした「実際に設立している人たち」のパターンや目的を紹介していきます。
1. 任意団体から法人化する人|活動の“信用力”を高めるために
地域のボランティア団体やサークル活動、大学の部活、OB会、同窓会などで、既にある程度の活動実績を持つ団体が、信用力アップを目的として一般社団法人を設立するケースはよくあります。
たとえば、子ども食堂やフードパントリー、地域の子育て支援団体など、地域密着の活動をしている団体。こうした団体は、活動自体が非営利であり、かつ継続的な支援を必要とすることが多いため、「寄付を募る」「助成金に応募する」「法人名義の銀行口座を開設する」といった場面で、法人格があるかどうかが大きな分かれ目になります。
任意団体のままでも活動は可能ですが、外部から見ると「誰が責任者なのか分からない」「お金の流れが不透明」という印象を持たれてしまうことも。
そこで「一般社団法人」という法人格を取得することで、書類上の信用力が一気に高まり、資金調達の面でも有利になります。
このように、“活動の継続と広がり”を意識した任意団体の法人化は、非常に自然な流れです。
2. 経営者・個人事業主が設立するケース|事業と社会的活動を“分けて”運営するために
すでに株式会社や個人事業を営んでいる方が、特定の事業を行う際の箱として一般社団法人を設立するケースも増えています。
たとえば、福祉や教育、地域活性化などの“社会的なテーマ”に取り組みたいとき、営利会社とは別の法人を立てることで、活動の趣旨を明確に分けることができます。
- 「本業は不動産業だけど、地域の子ども支援活動を法人として育てたい」
- 「自社のCSR(社会貢献)活動を、会社とは切り離して一般社団法人として展開したい」
- 「社員や取引先と一緒に、趣味やまちづくりの団体を立ち上げたい」
…といったように、営利法人とは別の器をつくることで、社会的な活動を独立した形で展開できます。
法人名義で助成金を申請したり、自治体などの委託事業を受けたりと、一般社団法人を“活動の主体”として活用するケースも少なくありません。
また、一般社団法人は利益を構成員に分配することができないため、営利法人とは異なる信頼性を持って活動することができます。
さらに、税務上「非営利型法人」として認められれば、法人税が収益事業のみに課されるなど、税制面でも有利になるケースがあります。
3. 行政・大学などと関わるために設立するケース
「法人格がないと受けられない仕事」がある
意外と多いのが、「個人や任意団体のままでは、相手にされない」という理由で設立を検討されるパターンです。
たとえば、自治体の委託事業、大学との共同研究、公的なイベントの協賛・主催などでは、「法人格を持っていること」が参加や契約の条件になっていることが少なくありません。
個人や任意団体の場合、外部からは「責任の所在が曖昧」「契約相手として不安定」と見なされてしまうため、公的機関や大企業とのやり取りにおいて不利になりやすいのです。
また、行政との関係だけでなく、「法人でなければ申請できない」「法人格が前提となっている」といった制度の要件がある事業もあります。
たとえば、障害者の相談支援事業などでは、法人格がなければ指定や補助金申請の対象とならない自治体も多く見られます。
つまり、「法人であること」が単なる形式ではなく、活動の入口そのものになっている分野も多く存在するのです。
4. 福祉・教育分野の事業者が制度的に一般社団法人を選ぶケース
「社団法人一択」ではないが、現実的な選択肢になることも多い
福祉や教育といった分野では、活動の性質上、「非営利の法人格であること」が求められる場面があります。
制度で明確に制限されているとは限りませんが、行政や地域団体との連携を前提とした場面では、非営利性のある法人格が選ばれる傾向があります。
このような場面でよく使われている法人格が、「NPO法人」と「一般社団法人」です。
NPO法人は、非営利法人として広く知られていますが、設立時に所轄庁の認証が必要で、申請から認証までに2〜3ヶ月程度かかることもあり、手続きも煩雑です。また、役員構成や報酬の制限、活動内容に関する要件なども設けられており、自由度はそれほど高くありません。
一方、一般社団法人であれば、所轄庁の関与はなく、定款認証と登記によって比較的スムーズに設立できるため、スピード感を重視する場面では特に選ばれやすい傾向があります。事業内容の自由度が高く、制度上の縛りも少ないため、実務上は取り回しのよい法人格として使われています。
そのため、以下のような方々が実際に一般社団法人を選択しています:
- 福祉系の有資格者が、相談支援や研修・啓発活動を行うために法人を設立
- 退職後に地域の福祉サービスを立ち上げた元福祉関連の職員
- 社会福祉士・臨床心理士など、専門職によるチームで立ち上げ
こうした分野では、「非営利で信頼性のある組織であること」が期待されるため、株式会社などの営利法人よりも、一般社団法人のほうが受け皿として選ばれやすいのが実情です。
5. 協会ビジネスを展開するために設立するケース
「◯◯協会」「◯◯アカデミー」など、講座・資格ビジネスの信用力アップに
最近では、自分自身の経験やノウハウを体系化し、講座や資格制度として提供する**“協会ビジネス”**の立ち上げに際して、一般社団法人を選ぶ人も増えています。
たとえば:
- 心理学・コーチング・キャリア支援などの分野で、認定講師制度を運営したい
- スクールや養成講座を法人化し、「◯◯協会」の名称でブランド力を出したい
- 受講者に“資格”を発行する仕組みを整えたい
このようなケースでは、株式会社よりも中立性・継続性・公共性のある一般社団法人の方が相性がよいとされ、行政との信頼関係や営業面でプラスに働くこともあります。
また、団体名に「協会」「学会」「機構」などの名称を使い易いのも、社団法人ならではの実務的メリットです。
私自身が上級相続診断士として会員登録している一般社団法人相続診断協会もこの協会ビジネスの一つです。
まとめ|一般社団法人は、目的に合わせて誰でも柔軟に設立できます
この記事でご紹介したように、一般社団法人は決して限られた人だけのものではありません。
今回ご紹介した例はほんの一部に過ぎません。
任意団体、個人事業主、経営者、福祉・教育の専門職など、それぞれの目的に応じて、さまざまな人が実際に法人化を選んでいます。
「活動をもっと広げたい」「信用力を高めたい」「助成金や委託事業に応募したい」――
そんな思いがあれば、社団法人は有力な選択肢になり得ます。
弊所には様々なご事情で一般社団法人の設立を検討されている方からのご相談を日々いただいております。
いざ設立しようと決めたとき、設立の手続きの煩雑さで中々動き出せないという方は是非弊所へご相談ください。
📌 あわせて読みたい関連記事
【設立関連コラム】
- 一般社団法人設立時の定款作成
- 一般社団法人の設立|人数・費用・必要書類・流れ・期間・定款
- 一般社団法人設立時の必要書類を司法書士が徹底解説
- 一般社団法人設立の流れ
- 一般社団法人の設立にかかる費用
- 一般社団法人の設立に必要な人数をケース別に解説
- 非営利型の一般社団法人とは?メリットと要件
- 一般社団法人の設立、誰に相談するのが正解?
- 一般社団法人の役員氏名に旧姓を併記するには?
- 一般社団法人で利用できる代表理事の住所非表示措置について
- 一般社団法人の主たる事務所の表記方法
- 実質一人社員で一般社団法人を設立する方法
- 一般社団法人の理事会設置の検討は慎重に
- 一般社団法人の「社員」とは?
- 任意団体から一般社団法人へ|信用力アップ・寄付金獲得のための法人化ガイド
- 一般社団法人の設立に必要な最低人数
- 一般社団法人の定款に記載する目的の記載方法と注意点
- 一般社団法人の名称の決め方|ルール・注意点・便利な調査方法
【運営関連コラム】
📘 著書(共著)
「一般社団法人設立・登記・運営がまとめてわかる本(日本法令)」