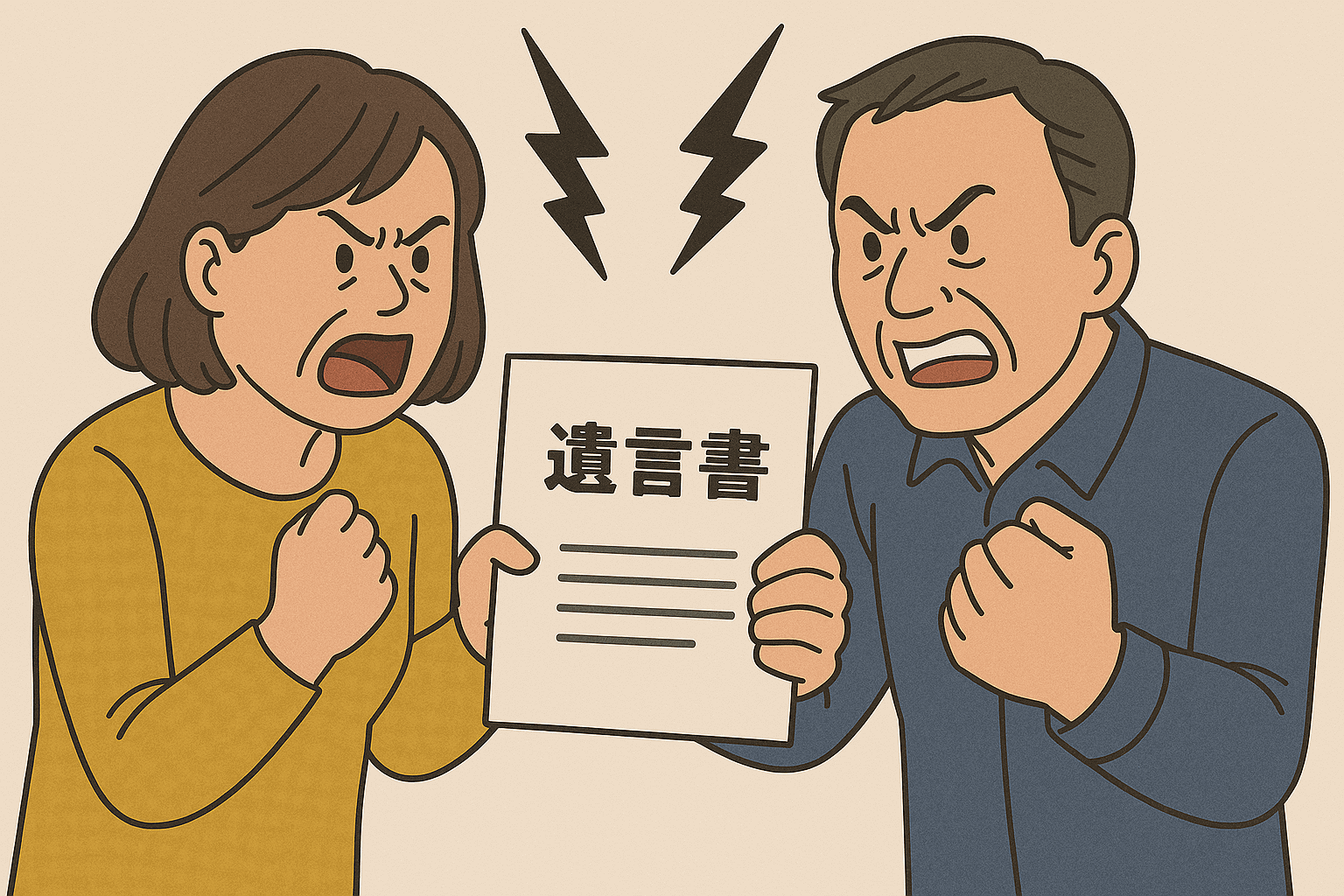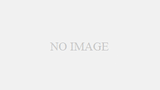「遺言書があれば、相続でもめない」
そう思っている方も多いかもしれません。たしかに遺言書は、相続人同士のトラブルを防ぐ有効な手段です。
しかし実際には、遺言書があることでかえって揉めてしまうケースも存在します。
その代表的な原因が、「遺留分(いりゅうぶん)」です。
この記事では、浦安市で遺言書の作成を検討している方に向けて、遺留分の基礎知識と、遺言書作成時に気をつけたいポイントを実務目線でわかりやすく解説します。
「遺留分」とは?法律で守られた“最低限の取り分”
「遺留分」とは、一定の相続人に保障された、最低限の取り分のことです。
たとえ遺言書で「全財産を長男に相続させる」と記載されていても、遺留分を有する他の相続人は、その財産価額の一部を(金銭で)取り戻すことができます。
この権利を「遺留分侵害額請求権」といい、令和元年7月の法改正前は「遺留分減殺請求(げんさいせいきゅう)」と呼ばれていました。
ここで大切なのは、「遺留分を侵害するような遺言書も有効である」という点です。
法律上、無効になるわけではありません。しかしその結果、他の相続人から請求がなされ、トラブルに発展するリスクがあります。
そもそも「遺言書がなかったらどうなるのか?」を知っておくことも大切です。
遺言書の役割や、なぜ書いておくべきなのかをわかりやすく解説した記事もぜひご覧ください。
▶ 浦安市で遺言書を考えるあなたへ|遺言書がないとどうなる?から学ぶ“備え”の重要性
遺留分について、国の制度や法改正の背景を詳しく知りたい方は以下も参考にしてみてください。
遺留分の対象となる相続人と割合
遺留分は、次の相続人に認められています:
- 配偶者
- 子(または孫などの代襲相続人)
- 直系尊属(父母・祖父母など)
※兄弟姉妹には遺留分はありません。
※相続放棄した人や相続欠格者・廃除された相続人も対象外です。
【遺留分割合の一覧】
| 相続人の構成 | 遺留分権利者 | 遺留分割合 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 配偶者 | 1/2 |
| 配偶者と子 | 配偶者 | 1/4 |
| 子 | 1/4(※人数で等分) | |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者 | 1/3 |
| 直系尊属 | 1/6(※人数で等分) | |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 1/2 |
| 兄弟姉妹 | 0(遺留分なし) | |
| 子のみ | 子 | 1/2(※人数で等分) |
| 直系尊属のみ | 直系尊属 | 1/3(※人数で等分) |
※たとえば、子のみが相続人となるケースで子が2人いる場合には、子の遺留分は1/4ずつ(=1/2 × 1/2)になります。
※同様に、直系尊属のみが相続人となるケースで直系尊属が2人いる場合には、1/6ずつ(=1/3 ×1/2)が遺留分です。
浦安市でも実際にある、遺留分トラブルの例
浦安市は首都圏近郊という土地柄、不動産が主な相続財産となるケースが多く見られます。
その場合、「不動産を誰か一人に相続させたい」という遺言書が、遺留分請求を引き起こす原因になることがあります。
【実例イメージ】
- 被相続人が「浦安市の自宅の土地・建物(評価額3,000万円)を長女に相続させる」と遺言
- 相続人は長女と長男
- 長男が「自分の遺留分(1/4=750万円)を請求」
- 長女に現金がなく、不動産を売るしかなくなる
- 結果、相続人同士の関係が悪化し長期トラブルへ…
遺留分トラブルを防ぐための遺言書の工夫

- 遺留分に配慮した分け方をする
他の相続人の遺留分を意識し、遺留分相当額以上の財産を相続させるとしておくことでトラブルの芽を摘むことができます。 - 付言事項で想いを伝える
「長年同居して世話になった長女に多く残したいと思いました」
といったメッセージを付け加えることで、感情的な対立の緩和につながります。 - 生命保険の活用
受取人を指定した生命保険は、原則として相続財産に含まれず、遺留分の対象外です。将来の遺留分請求への備えとして有効です。先の例では、(一定以上の金融資産があることが条件となりますが)長女を受取人とする生命保険に加入しておくことで、仮にご相続の発生後に長男から長女へ遺留分減殺額請求があった場合でも、受け取った保険金で請求額を支払うことができます。 - 生前に遺留分放棄をお願いする(要家庭裁判所の許可)
相続人の理解と合意が得られれば、家庭裁判所の許可を得て生前に遺留分を放棄してもらうことも可能です。ただし、この行為自体が家族関係を壊す原因に成りかねないので慎重な判断が必要です。 - 専門家と一緒に内容を検討する
浦安市では不動産の評価額が高いため、財産構成や家族関係に応じた遺言書の設計が重要です。相続専門の司法書士などと一緒に検討して進めることでご自身のご相続発生後に起こり得る争族を回避することができます。
遺言書で大切なのは「想い」と「配慮」のバランス
せっかくの遺言書が、残された家族の争いの火種になってしまっては本末転倒です。
自分の意思を伝えるだけでなく、法律に基づく遺留分や、家族への配慮も忘れないことが、円満な相続への第一歩です。
浦安市での遺言書作成なら、地元の司法書士へ
当事務所では、遺留分に配慮した遺言書の作成支援を行っています。
公正証書遺言や生命保険の活用、相続対策のご相談まで、地元・浦安市の事情に通じた司法書士が対応いたします。
司法書士の対応内容
- ご相談者様のご希望をヒアリング
- 法的リスクの検討・ご説明
- 相続トラブル防止に向けた事前対策のご提案
- 遺言書(案)を作成
- 公正証書遺言作成に必要な一切の事務手続きの代理
- (ご希望の場合のみ)相続専門税理士のご紹介
- (ご希望の場合のみ)遺言執行者の引き受け
- 浦安市内の不動産がある方への具体的なアドバイス
■ 遺言書作成支援の料金表
■ 初回相談無料|お気軽にどうぞ
→047ー712ー5713(お電話からのご相談予約)