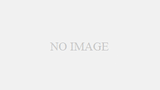一般社団法人の設立をご検討中のお客様から、定款のご相談を受ける際によく聞かれる質問のひとつに、次のようなものがあります。
「社員総会に出席できない社員が、書面やメールで意思表示したり、他の社員に議決権を委任したりすることはできますか?
定款にその旨を記載すべきでしょうか?」
今回はこの疑問に、法律と実務の両面からお答えしていきます。
✅ 代理人による議決権行使について
まず、「他の社員に議決権を委任する」こと、つまり代理人による議決権の行使については、定款への記載の有無に関わらず法律上認められている制度です。
根拠となるのは、一般法人法第50条です。
(議決権の代理行使)
第50条 社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を一般社団法人に提出しなければならない。
つまり、定款に定めがなくても議決権の代理行使は可能です。
ただし、代理人の資格を他の社員に限定したい場合には、定款に明記しておく必要があります。これは、総会屋や反社会的勢力の関与を防ぐための合理的な制限として認められています(代理人による議決権行使は、「自由にできることが原則」なので、その制限は合理的な範囲内でのみ認められます。)。
✅ 書面や電磁的方法による議決権の行使について
次に、書面や電子メールなどによる議決権の行使についてです。こちらは、代理行使と異なり、毎回の社員総会(の招集決定)ごとに「今回の総会では書面投票(又はメールなどの電磁的方法による投票)を認めるかどうか」を判断するルールになっています。定款に定める必要はありません。
原則は本人または代理人が社員総会に出席して議決権を行使する必要がありますが、社員総会の招集決定をする際に下記事項について定めることで書面若しくは電磁的方法若しくはその双方による議決権の行使ができるようになります。(一般法人法第38条)。
社員総会に出席しない社員が書面で議決権を行使できる場合は、その旨
電磁的方法(メールなど)での議決権行使を認める場合も同様に、その旨
また、書面や電磁的方法による議決権行使を認めた場合、以下の義務が法人側に課される点にも注意が必要です。
📌 書面投票を認めた場合の追加対応(抜粋)
社員総会の2週間前までに招集通知を発する義務(法39条1項ただし書)➡本来1週間前までに招集通知を発すればよかったところ、書面やメールで議決権を行使する人たちに考える時間を与えるため前倒しで送らなければいけない!
招集通知を書面で送る必要がある(法39条2項)➡理事会を設置しない一般社団法人では、本来招集通知が口頭でも許されるところ、書面で行わなければいけない。
参考書類の作成・送付義務(法41条・42条)➡書面やメールで議決権行使をする社員は社員総会での話し合いに参加できないので、当日出席しない社員が議決権行使の検討を十分にできるよう、必要な情報を書面で交付する義務がある。
社員総会開催日から3ヶ月間、議決権行使書面の備え置き義務(法51条3項)
✅ まとめ
代理人による議決権行使は定款に書かなくてもOK。ただし、代理人を社員に限定したい場合は定款に記載を。
書面・電磁的方法による議決権行使は、毎回の社員総会の招集決定時に判断が必要。
弊所ホームページには、一般社団法人に関して様々なテーマでコラムを随時掲載しています。
ご興味のある方は是非、他のコラムも読んでみてください!
(設立をご検討中の方へのお勧めコラム➡一般社団法人の設立を考えたら最初に読むページ)
📌 あわせて読みたい関連記事
【設立関連コラム】
- 一般社団法人設立時の定款作成
- 一般社団法人の設立|人数・費用・必要書類・流れ・期間・定款
- 一般社団法人設立時の必要書類を司法書士が徹底解説
- 一般社団法人設立の流れ
- 一般社団法人の設立にかかる費用
- 一般社団法人の設立に必要な人数をケース別に解説
- 非営利型の一般社団法人とは?メリットと要件
- 一般社団法人の設立、誰に相談するのが正解?
- 一般社団法人の役員氏名に旧姓を併記するには?
- 一般社団法人で利用できる代表理事の住所非表示措置について
- 一般社団法人の主たる事務所の表記方法
- 実質一人社員で一般社団法人を設立する方法
- 一般社団法人の理事会設置の検討は慎重に
- 一般社団法人の「社員」とは?
- 任意団体から一般社団法人へ|信用力アップ・寄付金獲得のための法人化ガイド
- 一般社団法人の設立に必要な最低人数
- 一般社団法人の定款に記載する目的の記載方法と注意点
- 一般社団法人の名称の決め方|ルール・注意点・便利な調査方法
【運営関連コラム】