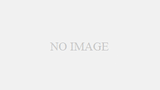一般社団法人を設立する際に必ず作成する定款。その中でも特に重要なのが「目的」の記載です。
一般社団法人では、営利企業である株式会社とは異なり、記載方法や注意点に独特のルールがあります。この記事では、目的の正しい書き方や、設立後に困らないためのポイントを、司法書士がわかりやすく解説します。
【1】「目的等」って何?株式会社との違い
一般社団法人を設立する際、定款に「目的」を記載することは必須です。
この「目的」は、株式会社などの営利法人にも存在する項目ですが、一般社団法人では少し書き方に違いがあります。
株式会社や合同会社の登記簿謄本を見ると「目的」とだけ表記されているのに対し、一般社団法人の登記簿では「目的等」という記載になります。
これは、一般社団法人の「目的等」が、
- (1)法人の設立目的(理念・活動趣旨)
- (2)その目的を達成するために行う具体的な事業内容
の2つの要素で構成されているためです。
つまり、「何のためにこの法人が存在するのか(目的)」と「それを達成するために何をするのか(事業内容)」をセットで定款に記載するのが、一般社団法人の一般的なスタイルです。
📝定款の記載例(目的等)
(目的) 第◯条 当法人は、地域の子育て支援を通じて安心できる地域社会の実現に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。 1 子育てに関する講座、イベント等の企画・運営 2 地域団体との連携による支援活動 3 前各号に附帯関連する一切の事業 4 その他当法人の目的を達成するために必要な事業
このように、まず理念的な目的を書き、その下に事業を列挙する構成が一般的です。
【2】記載がNGな目的とは?(許容されない例)
一見すると「自由に書けそう」な定款の目的ですが、法律上、記載してはいけない内容もあります。
❌ 一般社団法人の目的として許容されないもの
社員に利益を分配する営利目的
違法行為を目的とするもの(当然)
不明確で内容がわかりにくい目的
特に注意すべきなのが、「営利目的」です。
一般法人法第11条第2項では、
「社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない」
と明記されており、社員に利益を分配するような記載は無効とされます。
✅ 収益事業はOK!
とはいえ、一般社団法人が事業で収益を得ること自体はまったく問題ありません。
たとえば、講演会・物販・有料の研修サービスなどを行って収益を得ることも認められています。
これは、「非営利=収益をあげてはいけない」という意味ではなく、「収益をあげてもそれを社員に分配してはいけない」というルールだからです(理事や監事を兼任する役員が、役員としての業務の対価として役員報酬を受けるのは全く問題ないです)
【3】事業内容の決め方と優先順位
定款の目的等に記載する事業内容については、将来の展開を見据えて慎重に検討することが大切です。
以下のように優先度に応じて整理しておくと、記載内容を決めやすくなります。
事業内容の検討ステップ
| 区分 | 内容 | 定款記載の推奨度 |
|---|---|---|
| (A) | 設立直後から取り組む予定の事業 | 必ず記載する |
| (B) | 将来的に取り組む可能性が高い事業 | 記載を強く推奨 |
| (C) | 取り組むかは未定だが、念のため検討している事業 | 慎重に判断する |
「C」は注意が必要!
「いろいろできるようにしておきたい」と思って多くの事業を詰め込みすぎると、
・結局何を目的とした法人か分からない
・金融機関等とのやりとり(口座開設や融資)で不利に働く
というリスクがあります。
その法人が社会にどう関わっていくのかが伝わるよう、法人の設立目的との整合性を意識して記載しましょう。
登記後に事業を追加する場合のコスト
事業内容は、設立後に社員総会の特別決議+定款変更登記(登録免許税3万円)で追加・削除・変更が可能ですが、手間とコストがかかるため、最初の時点でしっかり設計するのがおすすめです。
【4】許認可が必要な事業は要チェック!
一部の分野では法人としての事業に行政の許認可が必要になる場合があります。
特に、一般社団法人は福祉や地域活動に取り組むことが多いですが、福祉事業を行うために指定申請が必要になることも少なくありません。そのため、次のような点に注意しましょう。
✅ チェックポイント
その事業に許認可が必要かどうか
申請先の官公庁が定款に特定の文言を求めていないか
同じ事業でも自治体ごとに記載方法が異なるケースがある
例:介護・保育・障がい福祉などの分野
これらの分野では、許認可申請の際に「定款の事業目的に○○という文言が必要です」と明記されていることがあります。
記載漏れがあると、あとから定款を修正・登記しなおさなければならず、手続きが遅れる原因になります。
事業に関係する官公庁のホームページをよく確認し、不明点があれば事前に問い合わせておくのがベストです。
【5】法人が設立時社員になる場合の目的の注意点
一般社団法人を設立する際、株式会社やNPO法人など法人が設立時社員となるケースもあります。
この場合、次の点に注意が必要です。
民法第34条の制限に要注意
「法人は、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」
つまり、法人は自らの目的の範囲内でしか他の法人を設立できないとされています。
したがって、設立する一般社団法人の目的が、設立時社員となる法人の目的と合理的に関連している必要があります。
✅ 完全一致までは不要
目的の一部が重なっていれば手続き上は問題ありません。
ただし、目的に全く関連性がない場合は、公証人から修正の指示を受ける可能性があるので注意が必要です。
✅ 不安なときは公証役場へ確認を
法人社員が関与する設立について不安がある場合は、事前に定款認証を行う公証役場に確認をとることをおすすめします。
✍️まとめ:目的の記載は「その法人らしさ」を決める最初の一歩
定款の「目的」は、単なる形式的な項目ではありません。
その法人が何のために存在し、何を目指すのかという“軸”になる大切な部分です。
記載を誤ると、将来の活動や許認可、資金調達に支障が出ることもあります。
だからこそ、設立前の段階でしっかりと目的と事業内容を整理しておくことが重要です。
不安がある場合は、是非司法書士への設立手続きのサポート依頼をご検討ください。
📌 あわせて読みたい関連記事
【設立関連コラム】
- 一般社団法人設立時の定款作成
- 一般社団法人の設立|人数・費用・必要書類・流れ・期間・定款
- 一般社団法人設立時の必要書類を司法書士が徹底解説
- 一般社団法人設立の流れ
- 一般社団法人の設立にかかる費用
- 一般社団法人の設立に必要な人数をケース別に解説
- 非営利型の一般社団法人とは?メリットと要件
- 一般社団法人の設立、誰に相談するのが正解?
- 一般社団法人の役員氏名に旧姓を併記するには?
- 一般社団法人で利用できる代表理事の住所非表示措置について
- 一般社団法人の主たる事務所の表記方法
- 実質一人社員で一般社団法人を設立する方法
- 一般社団法人の理事会設置の検討は慎重に
- 一般社団法人の「社員」とは?
- 任意団体から一般社団法人へ|信用力アップ・寄付金獲得のための法人化ガイド
- 一般社団法人の設立に必要な最低人数
- 一般社団法人の名称の決め方|ルール・注意点・便利な調査方法
【運営関連コラム】