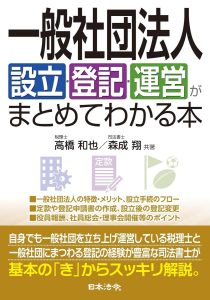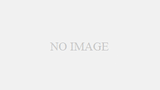一般社団法人を設立してどのような活動をしたいかは決まっているけれど、いざ設立手続きを進めようと思うと、何から始めたらいいのかわからない…
そんな方に向けて、このページでは一般社団法人の設立の流れ、費用、定款作成、必要書類などを、実際の流れに沿ってわかりやすく整理してご案内します。
これまで実際にお客様からいただいたご相談内容をもとに、設立をご検討される方がどんなステップを踏むのかをイメージしながら、ひとつずつ丁寧に解説しています。
各セクションには、より詳しく知りたい方向けに当サイトの関連コラムへのリンクもご紹介していますので、気になるテーマを個別に深掘りしていただくことも可能です。
「とにかく全体像を把握したい」「まずはざっくり知りたい」という方にもおすすめの構成となっています。
一般社団法人の設立で最初に決めるべきこと|通常型と非営利型の違い
一般社団法人の設立をご相談いただく際、最初に必ず確認するのが、「通常型」で設立するのか、「非営利型」で設立するのかという点です。
非営利型の一般社団法人を選択すると、収益事業に該当しない所得には法人税が課税されないという大きなメリットがあります。
ただしその反面、理事の人数要件が厳しくなる、法人税申告が複雑になるなど、デメリットや実務負担も増えるため注意が必要です。
また、この選択によって必要な定款の規定や役員構成にも影響が出るため、最初にしっかりと方針を決めておくことが大切です。
詳しくは以下のコラムで解説しています:
非営利型の一般社団法人とは?メリットと要件
一般社団法人の設立に必要な人数とは?|社員・理事・監事の役割も解説
次に、一般社団法人の設立に必要な人数についてご説明します。
まずは、設立時に登場する主要な立場の人たちをご紹介します:
- 社員: ⚠️従業員のことではありません。一般社団法人の社員総会を構成するメンバーです(※株式会社でいうところの「株主」に近い立場。ただし出資の概念はありません)。社員総会は法人の最高意思決定機関にあたるため、誰が社員になるかは非常に重要です。
- 理事: 一般社団法人の業務執行を担う役員です(株式会社でいう「取締役」に相当)。法人の実務や経営判断を行います。
- 監事: 一般社団法人の監督機関としての役員です(株式会社でいう「監査役」)。理事の業務が適正かどうかを監査し、計算書類などのチェックも行います。
なお、理事と監事は「役員」という点で共通していますが、両者の兼任はできません。
一方で、社員と役員の兼任は可能です(例:社員が理事や監事になることはOK)。
設立時に必要な最小人数
一般社団法人を設立する際、必要となる人数は以下の通りです:
| ケース | 必要人数 |
|---|---|
| 通常型(理事会なし) | 社員2名以上・理事1名以上 |
| 通常型(理事会あり) | 社員2名以上・理事3名以上・監事1名以上 |
| 非営利型(理事会なし) | 社員2名以上・理事3名以上(親族関係などないこと) |
| 非営利型(理事会あり) | 社員2名以上・理事3名以上(親族関係などないこと)・監事1名以上 |
このように、理事会を設置するかどうか、また非営利型かどうかによって、必要な人数が変わってきます。
下記のコラムもご参照ください:
定款作成について
設立メンバー(社員)が決まったら、定款の内容を決める必要があります。
定款は設立時の社員全員で作成するものです。一般社団法人の根本ルールを定める重要な書類であり、法人の運営にも大きな影響を与えます。
定款に必ず記載すべき7つの事項(絶対的記載事項)
法律上、定款に次の7項目を必ず記載することが求められています。
- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立時社員の氏名または名称および住所
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 公告方法
- 事業年度
これらが定められていない定款は無効になるため、注意が必要です。
ただし、これらの必須項目以外にも、実際に検討すべき事項は数多くあります。
実務上の検討事項や定款作成のポイントについては、下記のコラムで詳しく解説しています。
定款であらかじめ定めておくことによって、後々の運営上の負担を軽減できる内容などもご紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。
定款の認証手続きについて
定款の内容が決まったら、次に定款認証の手続きを進めます。
定款認証は、設立する一般社団法人の主たる事務所を管轄する法務局所属の公証人が行います。
ただし、公証役場にいきなり行ってその場で認証してもらえるわけではありません。事前の連絡・調整が必要です。
まずは、認証を希望する公証役場へ電話やメールで連絡を入れ、担当公証人の指示に従って進めていく形となります。
定款認証の際に必要となる書類や費用(一般的に5万2000円程)については、以下のコラムで詳しく解説しています:
設立登記に必要な書類の準備|必須書類とケースによる追加書類
定款の認証が完了したら、いよいよ設立登記の申請に向けて、必要な書類を準備・作成していきましょう。
設立登記に必ず必要な書類
- 登記申請書
- 公証人認証済みの定款
- 役員の就任承諾書
- 役員の印鑑登録証明書
- 印鑑届書
ケースに応じて必要となることがある書類
- 役員の本人確認証明書
- 設立時社員の決議書
- 設立時代表理事の選定に関する書面
これらの書類は、法人の機関設計や設立時の進め方によって内容や要否が異なる場合があります。
各書類の内容や必要性については、下記のコラムで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください:
いよいよ登記申請へ|申請先・設立日・登録免許税について
必要書類の準備・作成が整ったら、いよいよ設立登記の申請です。
申請先は、設立する一般社団法人の主たる事務所を管轄する法務局となります。
管轄の法務局は、下記のページから確認することができます:
都道府県(北海道を除く)を選択し、各ページ内にある「商業・法人登記管轄区域」から、設立予定の所在地に対応する法務局を確認してください。
原則は、登記申請を法務局が受け付けた日が、法人の設立日となります。
土日祝日や年末年始などの休庁日を設立日としたい場合は、特例申請が必要です。
土日・祝日・年末年始も一般社団法人の設立日にできるようになりました!
登記申請から登記完了までは通常1~4週間程度(申請先の法務局の申請件数の立て込み具合による)かかり、その後、登記事項証明書(謄本)の取得が可能になります。
なお、一般社団法人の設立登記にかかる登録免許税は6万円です。
登記完了後に必要な手続き一覧|設立後すぐに動くべきこと
法務局で登記が完了したら、法人の設立は法的に完了したことになります。
しかし、そこから実際に法人として活動を始めるためには、さまざまな届出や手続きが必要です。以下は登記完了後に行うべき代表的な手続きです:
- 法務局: 印鑑カードの交付申請、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書の取得
- 税務署・都道府県税事務所・市区町村役場: 法人設立届出書、青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 など
- 年金事務所: 健康保険・厚生年金の新規適用届、被保険者資格取得届、健康保険被扶養者届 など
- 銀行: 法人口座の開設(登記簿謄本・印鑑証明・定款などが必要)
期限内に行わないと、たとえば青色申告の資格が得られないというような不利益があるものもあるので、設立後は直ぐに手続きを行いましょう。
設立手続きのサポートをご希望の方へ|当事務所の対応内容
ここまで、一般社団法人の設立に必要な手続きについて解説してきました。
「難しそう」「やることが多くて大変そう」と感じられた方もいらっしゃるかと思います。
司法書士にご依頼いただくことで、お客様のご負担を大きく軽減することが可能です。
当事務所にご依頼いただいた場合、お客様にお願いする作業は以下のようにシンプルなものです:
- オンラインでの打合せ(Zoom等)
- 定款作成に必要な情報を記入するエクセルシートのご提出
- 印鑑証明書の取得(設立時社員および役員全員分)
- 司法書士作成の定款案をご確認・修正指示
- 届いた書類への押印と返送
※設立後の税務署・年金事務所等への届出については、お客様ご自身での対応が必要となりますが、必要に応じて税理士・社労士などの専門家をご紹介することも可能です。
一般社団法人の設立をご検討中の方へ
弊所は、一般社団法人の設立手続きに専門特化した司法書士事務所です。
「手続きがわからない・・・」
「非営利型で設立したいけど、どうすればいいの?」
「人数が多いので手続きに失敗したくない」
など、お悩みがあれば是非ご相談ください。
一般社団法人の設立に関する初回のご相談は無料です。
オンラインで全国からのご相談に対応しています。
📌 あわせて読みたい関連記事
【設立関連コラム】
- 一般社団法人設立時の定款作成
- 一般社団法人の設立|人数・費用・必要書類・流れ・期間・定款
- 一般社団法人設立時の必要書類を司法書士が徹底解説
- 一般社団法人設立の流れ
- 一般社団法人の設立にかかる費用
- 一般社団法人の設立に必要な人数をケース別に解説
- 非営利型の一般社団法人とは?メリットと要件
- 土日・祝日・年末年始も一般社団法人の設立日にできるようになりました!
- 一般社団法人の設立、誰に相談するのが正解?
- 一般社団法人の役員氏名に旧姓を併記するには?
- 一般社団法人で利用できる代表理事の住所非表示措置について
- 一般社団法人の主たる事務所の表記方法
- 実質一人社員で一般社団法人を設立する方法
- 一般社団法人の理事会設置の検討は慎重に
- 一般社団法人の「社員」とは?
- 任意団体から一般社団法人へ|信用力アップ・寄付金獲得のための法人化ガイド
- 一般社団法人の設立に必要な最低人数
- 一般社団法人の定款に記載する目的の記載方法と注意点
- 一般社団法人の名称の決め方|ルール・注意点・便利な調査方法
【運営関連コラム】
📘 著書(共著)
「一般社団法人設立・登記・運営がまとめてわかる本(日本法令)」