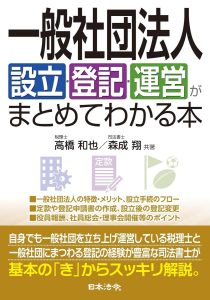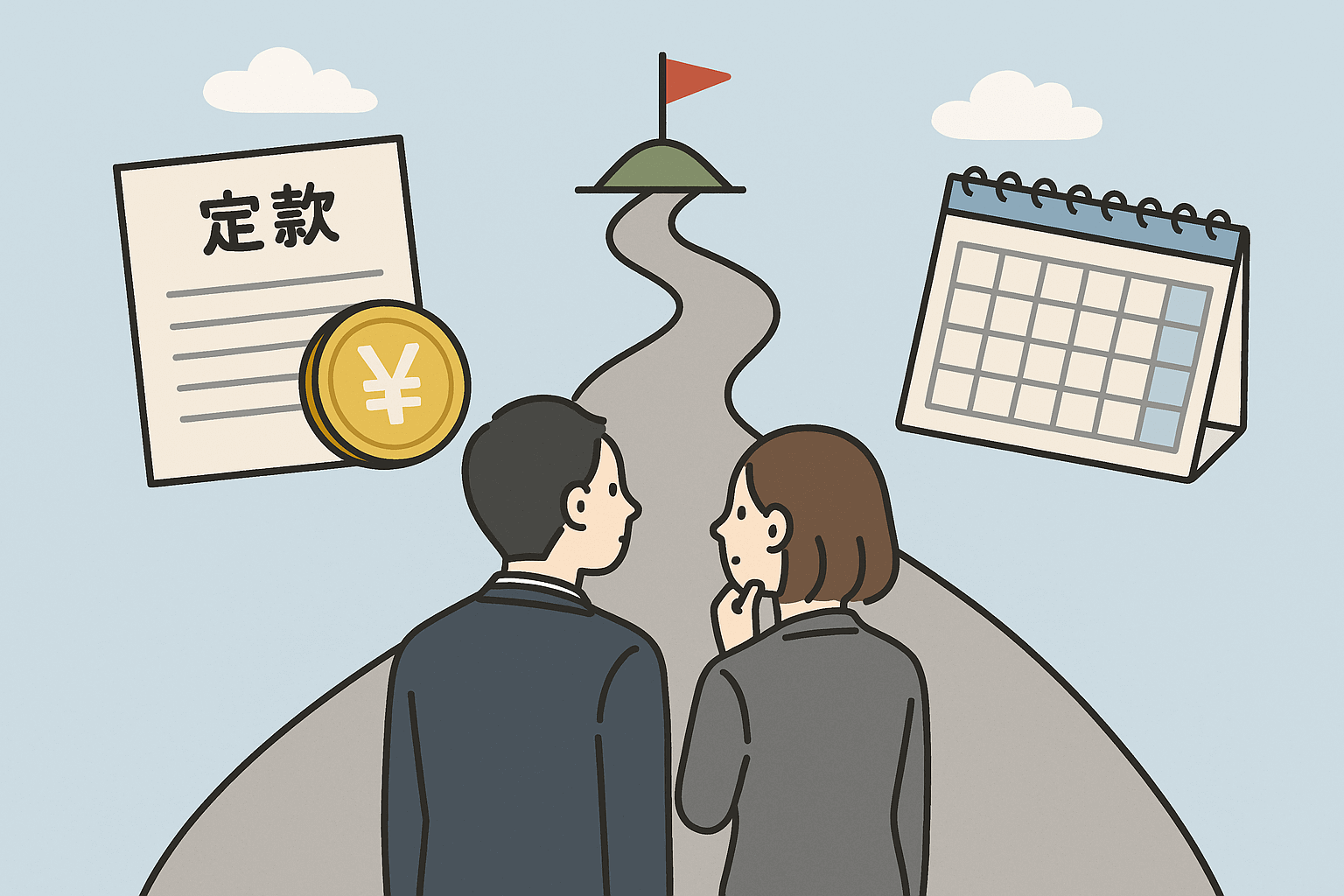一般社団法人の設立に必要な人数
一般社団法人の設立には、最低でも「社員(構成員)」が2名必要です。社員は法人の最高意思決定機関である「社員総会」を構成し、原則として1人1議決権を持ちます。つまり、誰を社員とするかは法人の将来を左右する重要な要素です。
✅ 最低限必要な人数構成
| 区分 | 人数 | 補足 |
|---|---|---|
| 社員(構成員) | 2名以上 | 議決権を持つ構成員。職員とは異なる。 |
| 理事(役員) | 1名以上 | 社員と兼任可。 |
※ 理事会を設置する場合は、理事3名以上+監事1名以上が必要です。
※ 非営利型の一般社団法人とするには、設立当初から理事3名以上などの条件を満たす必要があります。
設立に必要な書類と注意点
✅ 法務局へ提出する書類(登記申請時)
| 書類名 | 必要性 | 補足 |
|---|---|---|
| 登記申請書 | 必須 | 法務局に提出するメイン申請書 |
| 定款(認証済) | 必須 | 公証役場で認証済のものを提出 |
| 役員の就任承諾書 | 必須 | 理事や監事が就任を承諾したことを証明 |
| 役員の印鑑証明書 | 必須 | 原則有効期限はないが、法人実印の届出を行う代表理事については、発行後3か月以内のものを用意する必要がある |
| 印鑑届出書 | 必須 | 法人実印を登録するための書類 |
| 設立時社員の決定書 | 条件付き | 定款で「主たる事務所の所在場所」や「設立時役員」を定めていない場合に必要 |
| 設立時代表理事の選定書 | 条件付き | 理事会設置法人で、定款で代表理事を定めていない場合に必要 |
| 設立時役員の本人確認書類 | 条件付き | 印鑑登録証明書の添付が不要な役員については、住民票、戸籍の附票、運転免許証やマイナンバーカードに本人が原本証明をしたもの等を提出 |
✅ 公証役場で定款認証時に必要な書類
| 書類名 | 補足 |
|---|---|
| 定款3通(設立時社員全員の実印で押印) | 1通は登記用、1通は法人保管用、1通は公証役場保管用 |
| 設立時社員全員の印鑑証明書(原本) | 定款認証日時点で3か月以内に取得のもの |
| 実質的支配者の申告書 | 犯罪収益移転防止法に基づく提出物 |
| 社員が法人の場合の登記事項証明書 | 法人が社員となる場合に必要 |
一般社団法人の設立手続きの流れ【6ステップ】
一般社団法人は比較的設立しやすい法人形態ですが、登記までには複数の工程を踏む必要があります。
ここでは、一般的な設立の流れを6つのステップでわかりやすく解説します。
ステップ①:社員を2名以上決定する【法人の意思決定権を持つ中核メンバー】
一般社団法人の最高意思決定機関は「社員総会」です。
社員はこの社員総会を構成し、原則として1人1議決権を持ちます。つまり、社員を誰にするかは、法人の将来に直結する極めて重要なポイントです。
「とりあえず2人集めればいい」というものではなく、
その人物が法人の意思決定に関与する適切な構成員であるか、慎重に検討する必要があります。
ステップ②:定款を作成する
定款とは、法人の目的、組織、業務執行のルールなどを定める基本規程であり、まさに法人の“憲法”ともいえる存在です。
この定款は、設立時の社員全員の同意により作成されます。
内容によっては、銀行口座の開設や税務などに影響する場合もあるため、記載の仕方や条文構成には専門的な判断が求められることがあります。
ステップ③:定款を公証役場で認証してもらう
作成した定款は、公証人の認証を受ける必要があります。
これは一般社団法人の設立において、法律上必ず必要なステップです。
※株式会社と異なり、一般社団法人の定款は紙でも印紙不要です。
ステップ④:登記書類の作成
認証済の定款をもとに、法務局へ提出するための登記書類を準備します。
必要な書類については、【設立に必要な書類と注意点】で詳しく解説しています。
ステップ⑤:法務局へ登記申請【法人格がここで発生】
必要書類が整ったら、管轄の法務局へ登記申請を行います。
原則は、登記申請が受付けられた日が「法人設立日」となり、ここから法人格が発生します。
- 登録免許税:6万円(一律)
- 登記完了までは1〜3週間が目安(法務局の混雑状況により異なる)
ステップ⑥:設立後の諸手続き
登記が完了したら、以下のような実務手続きも必要です。
- 税務署・都道府県・市区町村への法人設立届出等
- 銀行口座の開設
- 必要に応じて、社会保険・年金事務所への届出
🔍 司法書士に依頼した場合、自分は何をすればいいの?
当事務所にご依頼いただいた場合、お客様にお願いする作業は以下のようにシンプルです。
- オンラインでの打合せ(Zoom等)
- 定款作成に必要な情報を記入するエクセルシートのご提出
- 印鑑証明書の取得(設立時社員および役員全員分)
- 司法書士作成の定款案をご確認・修正指示
- 届いた書類への押印と返送
※設立後の手続き(税務署・年金事務所等)については、ご自身での対応が必要です。
必要に応じて税理士・社労士などの専門家紹介も可能です。
一般社団法人の設立にかかる費用【自力 vs 依頼の比較】
✅ 設立費用の内訳(基本)
| 項目 | 金額の目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 60,000円 | 法務局に納める税金(固定) |
| 定款認証手数料 | 約52,000円 | 公証人手数料+謄本2通分 |
| 司法書士報酬 | 約90,000〜120,000円 | ※当事務所では10万円〜が目安です。 |
| 郵送費 | 3,500円〜(目安) | 設立当事者の人数・書類量により変動 |
✅ 自力で設立した場合の総額(概算)
約112,000円程度
(登録免許税+定款認証費用)
✅ 司法書士に依頼した場合の総額(概算)
約190,000円〜240,000円程度
(登録免許税+定款認証費用+司法書士報酬+郵送費など)
✅ その他費用(必要に応じて)
| 項目 | 金額の目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 印鑑証明書 | 1通500円(※2025年4月1日から) | 口座開設等で必要になる場合があるため、必要数を確認の上取得 |
| 法人用印鑑 | 3,000〜10,000円程度 | 登記申請前に必ず用意が必要 |
| 顧問税理士報酬 | 月額1万〜5万円程 | 税務処理が複雑になるケースでは顧問契約が推奨されます |
✅ よくある勘違い
「行政書士に頼めば安いのでは?」
→ 登記申請は司法書士の独占業務。行政書士に依頼すると、結局司法書士費用が別途発生し、費用が二重になるケースもあります。
一般社団法人の設立にかかる期間【目安と実務のリアル】
✅ 手続き別の所要期間(目安)
| 手続き | 所要期間 | 補足 |
|---|---|---|
| 社員・役員の決定 | 1日〜数日 | 家族・知人でスムーズに決まる場合は即日も可 |
| 定款の作成・調整 | 3日~数週間 | 規模が大きい法人は時間がかかる傾向 |
| 公証役場での認証 | 1日〜数日 | 公証人の予約状況による |
| 登記書類の作成・押印 | 2日〜5日 | 書類郵送・印鑑証明書の取得など含む |
| 法務局への登記申請〜完了 | 約1〜3週間 | 管轄法務局の混み具合によって変動 |
✅ トータルの目安
- スムーズに進めば2週間以内に登記申請まで可能
- 通常は1か月程度
✅ 司法書士に依頼した場合のスピード感
- スケジュール設計から定款設計、公証役場の予約、登記までまとめて対応
- 書類の不備リスクを最小限にできるため、想定以上に早く進められるケースも多い
定款ってなに?なぜそんなに大事?
定款とは、一般社団法人の目的や組織運営のルールを定めた最も重要な書類です。
いわば、法人の“憲法”のようなもので、法人の活動や意思決定はこの定款に基づいて行われます。
✅ 一度作ったら簡単には変えられない
定款の内容を変更するには、社員総会での特別決議(総社員の半数以上かつ、総社員の議決権の3分の2以上の賛成)が必要です。
さらに、目的や商号、主たる事務所の所在地などを変更する場合は、法務局での登記(有料)も必要になります。
✅ 定款の内容によるトラブル例
- 非営利型の一般社団法人として設立したつもりだったが、定款上の要件を満たしていなかった
- 銀行口座の開設や許認可の申請で、目的の記載内容がネックになった
よくある質問・お悩みQ&A
Q. 一般社団法人を家族だけで設立できますか?
A. はい、可能です。 社員2名以上、理事1名以上の要件を満たせば、親子や夫婦だけでも設立可能です。ただし構成は慎重に検討を。
👉 実質一人社員で一般社団法人を設立する方法
Q. 最低いくらあれば設立できますか?
A. 自力:約11万円、司法書士に依頼:約19〜24万円が目安です。
Q. 社員と理事は兼ねても大丈夫ですか?
A. はい、兼任可能です。 社員2名のうち1名が理事を兼任する形でも問題ありません。
Q. 設立後すぐに活動しなくても大丈夫?
A. 法的には問題ありませんが、口座開設や実績が求められる場面では不利になることもあります。
Q. 設立後にすぐやるべきことは?
A. 以下のような手続きが必要になります:
- 税務署・都道府県・市町村への法人設立届出
- 銀行口座の開設
- 必要に応じて社会保険や年金事務所への届出
Q. 非営利型の一般社団法人にするにはどうしたらいい?
A. 定款の内容と、実際の運営実態の両方が重要です。
たとえば、理事が3名以上いること、剰余金の不分配・残余財産の帰属先を公益法人等とすることを定款に明記することなどの要件を満たしている必要があります。
👉 非営利型の一般社団法人とは?メリットと要件
Q. 相談すべきか分からない…
A. 以下のような方は、一度相談しておくとスムーズです:
- 非営利型で設立したい
- 社員構成や定款の内容に不安がある
- 自力で進める時間・手間をかけたくない
まとめ
一般社団法人の設立は、出資金に関する手続きが不要な分、「株式会社より簡単」と思われることもありますが、定款設計や社員構成など注意すべき点は多く、専門的な視点が欠かせません。
また、「とりあえず設立できた」だけではなく、信頼される法人として継続的に活動できるかどうかが重要です。
一般社団法人の設立をご検討中の方へ
弊所は、一般社団法人の設立手続きに専門特化した司法書士事務所です。
「手続きがわからない・・・」
「非営利型で設立したいけど、どうすればいいの?」
「人数が多いので手続きに失敗したくない」
など、お悩みがあれば是非ご相談ください。
一般社団法人の設立に関する初回のご相談は無料です。
オンラインで全国からのご相談に対応しています。
👉 詳しくはこちらのページもご覧ください:
一般社団法人設立のご案内ページへ
📌 あわせて読みたい関連記事
【設立関連コラム】
- 一般社団法人の設立を考えたら最初に読むページ
- 一般社団法人設立時の定款作成
- 一般社団法人の設立|人数・費用・必要書類・流れ・期間・定款
- 一般社団法人設立時の必要書類を司法書士が徹底解説
- 一般社団法人設立の流れ
- 一般社団法人の設立にかかる費用
- 一般社団法人の設立に必要な人数をケース別に解説
- 非営利型の一般社団法人とは?メリットと要件
- 土日・祝日・年末年始も一般社団法人の設立日にできるようになりました!
- 一般社団法人の設立、誰に相談するのが正解?
- 一般社団法人の役員氏名に旧姓を併記するには?
- 一般社団法人で利用できる代表理事の住所非表示措置について
- 一般社団法人の主たる事務所の表記方法
- 実質一人社員で一般社団法人を設立する方法
- 一般社団法人の理事会設置の検討は慎重に
- 一般社団法人の「社員」とは?
- 任意団体から一般社団法人へ|信用力アップ・寄付金獲得のための法人化ガイド
- 一般社団法人の設立に必要な最低人数
- 一般社団法人の定款に記載する目的の記載方法と注意点
【運営関連コラム】
📘 著書(共著)
「一般社団法人設立・登記・運営がまとめてわかる本(日本法令)」