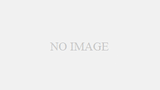一般社団法人の設立を検討する際、一般社団法人の代表理事に就任することを検討する際、消極的になってしまう理由の一つに
『代表理事の住所が登記されてしまうこと』
があると思います。
設立や役員変更のご相談をいただく際に
「代表者の住所を非表示にすることができるようになったって聞いたんですが?」
と聞かれることが少なくありません。
実は、法人代表者の住所非表示に関する改正については、令和4年から令和6年にかけて2回行われています。
このうち、一般社団法人にも適用されるものと、一般社団法人には適用されないものがあります。
本コラムでは、各改正の概要、一般社団法人の代表理事における利用可否、利用できるものについてはその方法を解説します。
直近(令和6年10月1日施行)の改正について
ご相談者様が
「代表者の住所を非表示にすることができるようになったって聞いたんですが?」
と尋ねてくるのは、圧倒的にこちらの改正についてが多いです。
制度の概要
株式会社の設立時、代表取締役の就任(重任)時・住所移転時、他の法務局の管轄区域内への本店移転時に所定の書面(本店所在地の実在性を証明する書面、代表取締役等の住所を証明する書面及び実質的支配者の本人特定事項を証する書面)を添付して申し出ることにより、特段の理由なく、株式会社の代表取締役等の住所を非表示にできる制度です。
一般社団法人における利用の可否
(令和7年6月18日現在)株式会社のみに適用することのできる制度のため、一般社団法人では利用することができません。
今後更に法改正が入り、利用できる範囲が拡大され、一般社団法人にも適用される可能性は十分にあると思います。
令和4年9月1日施行の改正について
制度の趣旨
会社・法人の代表者である方のうち、DV、ストーカーによる被害、又はこれに準ずる被害(虐待、交際相手からの暴力等)によって、特定の人から住所を知られてしまうことで危害・損害が及ぶ恐れのある方(以下、「被害者等」といいます。)について、登記上の個人住所を非表示にすることによってその保護を図る制度です。単に被害を受けていることを法務局に申告するだけでは利用できず、「住所が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあることを証する書面」を添付して申告しなければいけません。
一般社団法人における利用の可否
一般社団法人においても利用することができます。
住所が明らかにされることにより被害を受ける恐れがある方の保護については、株式会社でも一般社団法人でも変わりはないからです。
利用する方法
法人の管轄法務局に申出をします。
申出書の記載内容
- 法人の名称及び主たる事務所の所在場所
- 申出人の資格、氏名、住所及び連絡先
- 被害者等の資格、氏名、住所及び連絡先
- 代理人によって申出をするときは、代理人の氏名、住所及び連絡先
- 住所非表示措置を希望する旨及びその理由
- 申出の年月日
申出書のひな形はこちらの1ページ目(住所非表示措置申出書.pdf)
申出書の添付書面
- 住所が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあることを証する書面
- 申出書に記載されている被害者等の氏名及び住所が記載されている市区長村長その他の公務員が職務上作成した証明書(住民票の写し、戸籍の附票、被害者等本人が原本証明した運転免許証・マイナンバーカードの写し)
- 委任状 ➡ 司法書士などの代理人が代理申請をする場合
補足:住所が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあることを証する書面とは?
法務省の通達には下記のとおり記載されています。
- 市区町村が発行しているDV等支援措置決定通知書
- ストーカー規制法に基づく警告等実施書面
- 配偶者暴力相談支援センターのDV被害者相談証明
実際の流れ
過去、私が住所非表示措置の申出を行った際の流れを参考までに記載します。
- ストーカー等の被害を受けている方本人が、管轄の警察署へ行って、被害を受けていることを相談する(その際に必ず警察で相談の記録を残してもらいます)
- ストーカー等の被害を受けている方本人が、市区町村役場の市民課窓口で、DV等の支援措置申出をする
- 区役所から管轄の警察署へ、申出人から相談があったことの確認が入る
- 区役所で支援措置申出が受理される
- 申し出から1か月半~2か月ほど経った後、申出人の自宅に「支援措置申出決定通知書」が届く
- 5の書類を添付書面として、法務局に住所非表示措置申出を行う
※なお、個人住所のお引越しをされるタイミングで支援措置申出を行う場合は、住民票の移転をする前に新住所の管轄警察署へ相談に行き、その後、住民票の移転と同時に市区町村役場の窓口で支援措置の申出を行うようにしてください。こうすることで、新住所への住民票の移転と同時に住民票の閲覧に制限がかかります(支援措置の決定がされるまでの間も住民票が第三者に見られる恐れがなくなる)。住民票の移転をした後に警察署へ行って、その後に支援措置申出をすると、住民票の移転から支援措置申出までの間住民票の閲覧に制限がかからないため、第三者に住民票を閲覧されてしまうリスクがあります。
申し出がされた場合の登記記録例
次のようなかたちで登記がされます。
一般社団法人等登記規則第3条において準用する商業登記規則第31条の2の規定による措置 代表理事 森 成 翔
住所非表示措置の終了
住所非表示措置は、次のいずれかの場合は終了します。
- 被害者等から住所非表示措置を希望しない旨の申出がされたとき
- 住所非表示措置をした年の翌年から3年が経過したとき
補足:住所非表示措置がされた翌年から3年が経過した後も引き続き非表示措置を続けたいときは?
非表示措置が終了する前に、登記官から被害者等の申出のあった住所に宛てて、期間満了のお知らせが届きます。
引き続き、非表示措置を希望する場合は、期間満了の前に再度非表示措置の申出をする必要があります。
非表示措置の申出をした後に住所を移転したときは?
非表示措置の申出をした後、別の住所へお引越しをした場合、その移転登記は必要です。
この時に気を付けなければいけないことは、新しい住所について非表示措置をしたい場合、改めて先ほどの流れで新住所について非表示措置申出を行う必要がある(通常は、代表理事の住所変更登記を併せて行う)ということです。
なにもせずに代表理事の住所変更登記のみをしてしまうと、新しい住所が露になってしまうので、気を付けましょう。
他にできることはあるか?
ここまでお話ししたとおり、一般社団法人の代表理事の住所については、住所が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあることを証する書面を添付できる方以外は利用することができません。
では、ほかに何かできることはないのでしょうか。
少しだけあります。
マンションやアパートなど区分建物に居住されている代表理事の方については、その個人住所を登記する際、建物名・部屋番号などの所謂「方書き」については省略することができます。
たとえば、住民票上の住所が、
千葉県浦安市北栄七丁目7番7号北栄マンション707号室
となっている場合に、
千葉県浦安市北栄七丁目7番7号
と登記することは可能です。
小さな省略ですが、区分建物に居住している場合に部屋番号まで特定されているかどうかは割と大きな違いがあると思いますので、代表理事の住所を登記する際は是非検討してみてください。
まとめ
令和6年10月1日から施行された株式会社の代表取締役住所非表示措置は、株式会社のみ利用のできる制度であり、一般社団法人では現在のところ利用ができません(今後の改正で一般社団法人も利用できるようになる可能性はあり)。
一方、DV、ストーカー、虐待等の被害を受けている方の保護を図る為に令和4年9月1日から施行された住所非表示措置の制度は一般社団法人でも利用することができます。
この制度が利用できない場合でも区分建物に居住されている代表理事の方については、建物名部屋番号などの方書き部分は省略して登記をすることができます。
住所非表示申出は、設立時、役員変更時、代表者の住所変更時などに登記申請と併せて行うのが効果的です。
(設立手続きについて詳しくはこちら➡一般社団法人の設立を考えたら最初に読むページ)
(役員変更について詳しくはこちら➡一般社団法人の理事改選)
📮 お問い合わせはこちらから
会社の設立、役員変更、代表理事の住所変更登記のご相談はもちろん、これらの手続きと併せて令和4年9月1日施行の住所非表示措置(DV、ストーカー等の被害からの保護のための住所非表示措置)を検討されている方は、是非ご相談ください。
- 📩 お問い合わせフォームはこちら
- 💬 LINEで相談する(ID:@aeq0295u)
- 💼 Chatworkで連絡する
- 💬 SlackでDMを送る
- 📞 お電話:047-712-5713
- 💰 法人登記の料金表を見る
【運営関連コラム】
- 一般社団法人のオンライン社員総会の開催方法
- 一般社団法人のみなし社員総会(書面決議)
- 一般社団法人の役員任期切れていませんか?
- 一般社団法人の役員任期の考え方、確認方法と注意点
- 一般社団法人の理事会廃止の手続き及び費用
- 一般社団法人の役員氏名に旧姓を併記するには?
- みなし解散された一般社団法人を復活させる方法とその費用
【設立関連コラム】