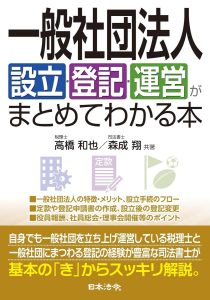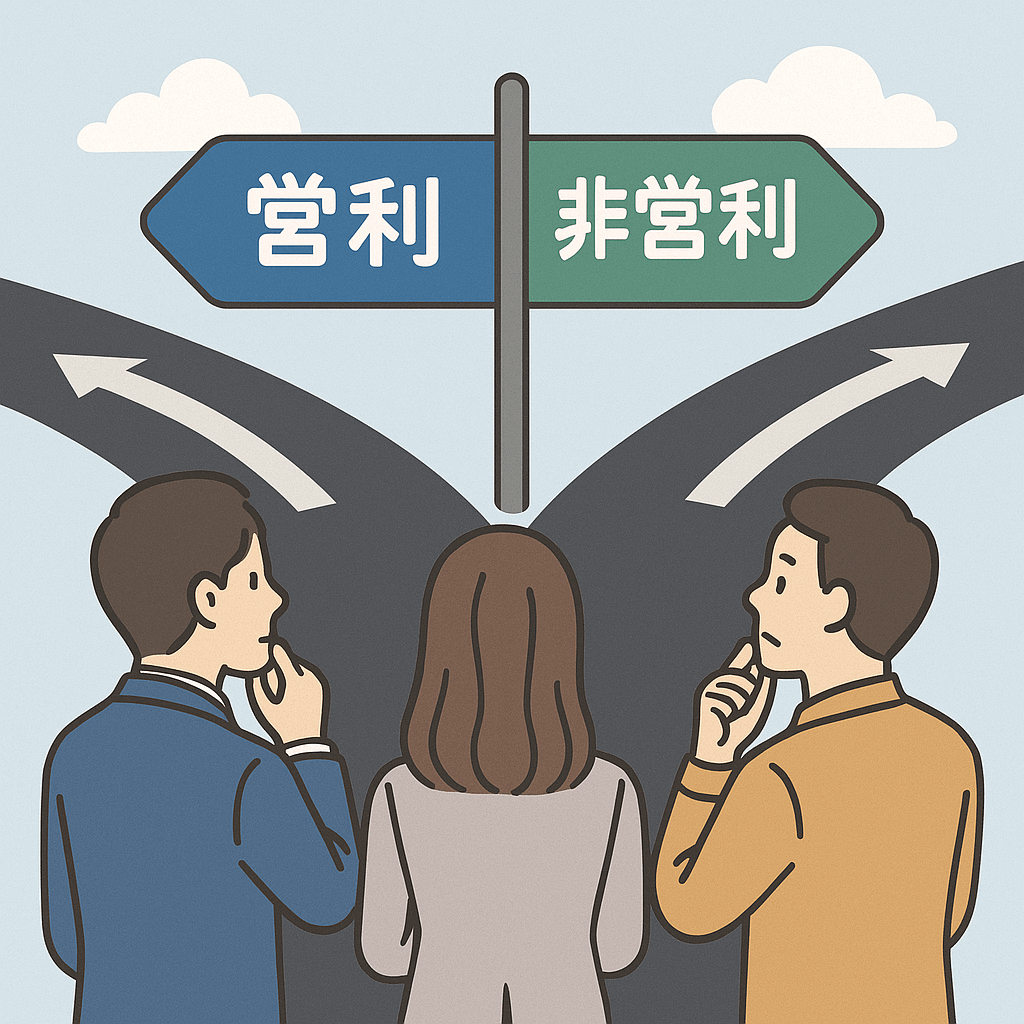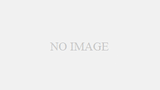一般社団法人という法人形態を選択して法人設立をする方が、一般社団法人を選ぶ理由の大きな1つとして、非営利型の一般社団法人を設立したいからというものがあります。
「非営利型一般社団法人」は税制面でのメリットがあります。しかし、要件を満たしていなければ、そのメリットを享受することはできません。
この記事では、非営利型一般社団法人のメリット・デメリット、要件を詳しく解説し、特に設立時に失敗しないためのポイントをお伝えします。
非営利型の一般社団法人とは
最初に非営利型の一般社団法人とは何かについて、説明します。
一般社団法人を大きく区分けすると次の2種類があります。
- 法人税法上の非営利型法人の要件を満たすもの(非営利型の一般社団法人)
- 1以外のもの(通常の一般社団法人)
2の通常の一般社団法人は、株式会社と同じようにすべての所得に対して課税がされます。
一方、1の非営利型の一般社団法人の場合は、34種の収益事業に該当しない所得に対しては課税されません。
(収益事業は、一般社団法人・ 一般財団法人と法人税(国税庁)のP3を参照)
非営利型の一般社団法人のメリット
非営利型の一般社団法人のメリットは、前記のとおり、収益事業に該当しない所得については課税されないことです。
たとえば、一般社団法人の場合、会費収入で運営するケースも少なくないですが、会費収入は一般論として収益事業に該当しません(個別具体的な判断は、必ず税理士さんへ確認をお願いします)。
会費収入の金額や割合が大きい法人では、この収入が非課税になるというのは大きなメリットと言えるでしょう。
非営利型の一般社団法人のデメリット
前期のようなメリットがあるのであれば、確実に非営利型の一般社団法人を選んだ方がいいと思われるかと思いますが、次のようなデメリットもあります。
- (後述する非営利性が徹底された法人の場合)法人の利益を社員に還元することができない。
- 非営利型の要件を満たし、それを維持するのが大変。
- 法人税申告が複雑になる。
1については、後述する非営利性の徹底された非営利型の一般社団法人を選んでいる場合、法人を解散するときにその他の場合と違いがあります。
一般社団法人は、通常型、非営利型関係なく、「社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない(一般法人法11条2項)」という法律の規定があるため、法人の存続中は社員に利益を分配することは禁じられています。
しかし、法人を清算する場合は、法人に残っている利益を社員総会の決議により、処分することができます。
「定款の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会の決議によって定める(一般法人法239条2項)。」となっており、社員総会の決議では、社員に分配する方法も認められています。
ただし、非営利性の徹底された非営利型の一般社団法人を選択している場合、ここに制限がかかります。
上記の話をするとよくお客様から
「じゃあ、どうやって法人の利益を法人の活動に貢献している人に還元すればいいのですか?」
と質問を受けますが、制限されているのは、社員に利益を分配する行為(株式会社でいうところの株主に剰余金を分配する行為)ですので、たとえば中心メンバーである理事の方々に適正な役員報酬を支払うことや、法人の従業員の方に適正な給与の支払いをすることはなんら禁じられていません。
2については、詳しくは後述しますが、非営利型の一般社団法人は、理事の人数要件があります。
これは、一時的なものでな許されず、非営利型の一般社団法人として存続する間は維持されなければいけません。
理事の不測の退任などによって要件が満たされなくなってしまうことの無いよう、理事になるメンバーを慎重に選出する必要があります。
3について、まず前提として、非営利型の一般社団法人を選択した場合も収益事業を行うことはできます。
そして、法人の所得に収益事業による所得と、収益事業以外の所得の双方がある場合は、収益事業での所得についてのみ法人税申告が必要になります。
そもそも何が収益事業に該当するのかという判断が税務知識のない人にとっては非常に難しいですし(私もわかりません)、実は税理士さんの中でも非営利型の一般社団法人の税務申告に慣れている人でないと困惑してしまうケースが多いようです。
非営利型の一般社団法人の要件
次に非営利型の一般社団法人の要件を解説します。
非営利型の一般社団法人には更に次の2つの区分けがあります。
- 非営利性が徹底された法人
- 共益的活動を目的とする法人
それぞれの要件は下記のとおりです。
| 類型 | 要 件 |
|---|---|
| 非営利性が徹底された法人 | 1 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。 |
| 2 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。 | |
| 3 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。 | |
| 4 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。 | |
| 共益的活動を目的とする法人 | 1 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。 |
| 2 定款等に会費の定めがあること。 | |
| 3 主たる事業として収益事業を行っていないこと。 | |
| 4 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。 | |
| 5 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。 | |
| 6 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。 | |
| 7 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。 |
以下、補足します。
【共通の事項】
「各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。」については、以下のことに注意しましょう。
- 非営利型の一般社団法人を選択する場合、理事は最低でも3人以上必要
- 理事が3人の場合、その3人はお互いに配偶者関係や3親等内の親族関係があってはいけない(仮に理事の中に自分と自分の3親等内の親族が1名いる場合は、3分の1以下の要件を満たすため、理事の総数を6人以上にしなければならない)
(関連コラム➡一般社団法人の設立に必要な人数をケース別に解説)
【非営利性徹底型】
1の要件を満たすために定款には、下記のような記載をします。
(剰余金の不分配)
第●条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
2の要件を満たすために定款には、下記のような記載をします。
(残余財産の帰属)
第●条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
【共益的活動目的型】
「会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的」とは、学校の同窓会などを一般社団法人化するようなケースが典型例です。
共益的活動目的型は、非営利性徹底型と異なり、剰余金の不分配や残余財産の不分配についてを定款に定めることまでは求められていません。
こちらは、必ず会費(入会金・月会費・年会費等)の定めを定款に置く必要があり、また主たる事業として収益事業を行うことが制限されます。
まとめ
今回の記事では、非営利型の一般社団法人とは何か、選択するメリット・デメリットは何か、非営利型の一般社団法人の要件について解説しました。
弊所以外で一般社団法人を設立したお客様からのお問い合わせで、「本当は非営利型の一般社団法人として設立したかったのですが、対応した専門家の方があまりよくわかっていなかったようで・・・」と非営利型の要件を満たしていない状態で設立されてしまいご相談に来られる方も少なくありません。
司法書士の中でも非営利型の一般社団法人について認識していない者も少なくないため、この部分について検討されずに設立をされてしまうケースがあるようです。
設立後に通常型の一般社団法人から非営利型の一般社団法人へ移行することもできますが、次のような手間と費用がかかってしまいます。
・事業年度中に営利型⇨非営利へ移行する場合、非営利型の一般社団法人へ移行する日付で新たな事業年度を開始しないといけない(その前日までで事業年度が一旦終了するので法人税申告その他の税務届けが必要になり、税理士へ依頼する場合は税理士費用がかかる)
・理事の人数要件を満たしていないケースが多いので、理事の選任手続きを行わなければいけない(手間がかかるだけでなく、登録免許税や司法書士に依頼する場合の司法書士報酬がかかる)
・定款の変更が必要(定款変更は定時株主総会の特別決議により行うが、手続きについて司法書士の支援が必要な場合は費用がかかる)
設立後に余計な費用や手間がかからないよう、設立時にしっかり設計した上で、手続きをしましょう。
一般社団法人の設立をご検討中の方へ
弊所は、一般社団法人の設立手続きに専門特化した司法書士事務所です。
「手続きがわからない・・・」
「非営利型で設立したいけど、どうすればいいの?」
「人数が多いので手続きに失敗したくない」
など、お悩みがあれば是非ご相談ください。
一般社団法人の設立に関する初回のご相談は無料です。
オンラインで全国からのご相談に対応しています。
📌 あわせて読みたい関連記事
【設立関連コラム】
- 一般社団法人の設立を考えたら最初に読むページ
- 一般社団法人設立時の定款作成
- 一般社団法人の設立|人数・費用・必要書類・流れ・期間・定款
- 一般社団法人設立時の必要書類を司法書士が徹底解説
- 一般社団法人設立の流れ
- 一般社団法人の設立にかかる費用
- 一般社団法人の設立に必要な人数をケース別に解説
- 一般社団法人の設立、誰に相談するのが正解?
- 一般社団法人の役員氏名に旧姓を併記するには?
- 一般社団法人の主たる事務所の表記方法
- 実質一人社員で一般社団法人を設立する方法
- 一般社団法人の理事会設置の検討は慎重に
- 任意団体から一般社団法人へ|信用力アップ・寄付金獲得のための法人化ガイド
- 一般社団法人の設立に必要な最低人数
【運営関連コラム】
📘 著書(共著)
「一般社団法人設立・登記・運営がまとめてわかる本(日本法令)」