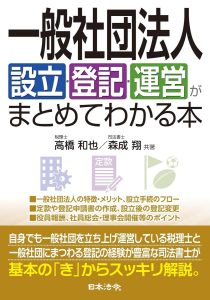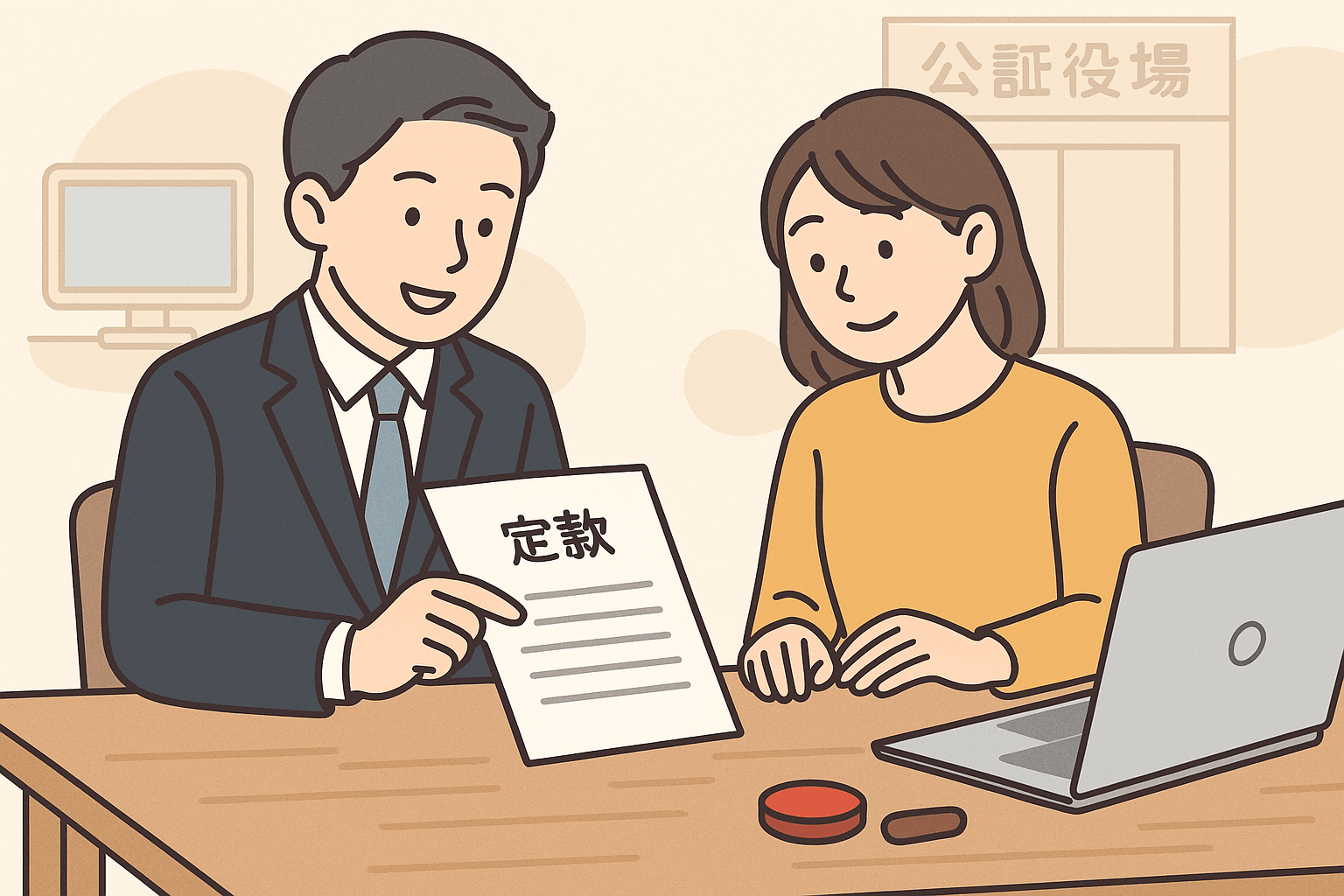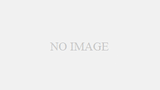本コラムでは、一般社団法人の設立時に作成する定款について詳しく解説します。
- 機関設計に関するもの
- 経費の負担(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」)27条)
- 任意退社に関する別段の定め(一般法人法28条)
- 法定退社の事由(一般法人法29条1号)
- 電子提供措置をとる旨の定め(一般法人法47条の2)
- 社員総会の議決権の数に関する別段の定め(一般法人法48条)
- 定足数に関する別段の定め(一般法人法49条)
- 役員の任期に関する定め(一般法人法66条、67条)
- 代表理事及び業務執行理事の理事会への自己の職務執行状況の報告に関する定め(一般法人法91条2項)
- 理事会議事録への署名又は記名押印義務者に関する規定(一般法人法95条3項)
- 理事会の決議省略に関する定め(一般法人法第96条)
- 理事等による損害賠償責任の一部免除に関する定め(114条1項)及び責任限定契約に関する定め(115条1項)
- 基金に関する定め(一般法人法131条)
一般社団法人の定款作成の流れ
最初に定款作成の流れについてみていきましょう。
一般社団法人の設立時に登記の添付書類として提出する定款には公証人の認証を受けなければなりません。
公証人の認証を受けるまでのおおまかな流れは次のとおりです。
1 設立時社員を2名以上決める
一般社団法人を設立するには必ず2名以上の設立時社員が必要です。
したがって、定款作成のスタートは、設立時社員を2名決定するところからはじまります。
(関連記事➡一般社団法人の設立に必要な人数をケース別に解説)
(関連記事➡実質一人社員で一般社団法人を設立する方法)
(関連記事➡一般社団法人の「社員」とは?)
2 定款内容を決める
設立時社員が確定したら、設立時社員の全員で定款を作成します。
定款で決定する内容は多岐にわたります。
ここを雑にして設立をしてしまうと、設立後に思いもよらぬ手間や費用がかかることも多々あります。
一般社団法人の設立手続きの中でも特に重要な箇所になります。
3 定款認証を受ける公証役場で、定款の事前チェックを受ける
定款が完成したら、定款認証を受ける公証役場で定款の事前チェックを受けます。
定款のデータは公証役場にメール・FAXで送ります。
定款認証は、設立する一般社団法人の所在地を管轄する法務局・地方法務局に所属する公証人が行います。
各公証役場がどこの法務局の所属になっているかは、下記ページからご確認いただけます。
4 定款に押印する
定款の事前チェックを受けたら、定款内容を確定して、設立時社員の全員で定款に押印・契印をします。
5 公証役場で定款認証をする
公証役場と定款認証日を調整して、公証役場で定款認証をします。
法人の設立日が決まっている場合は、設立日以前に定款認証が完了している必要があります。
一般社団法人の定款認証手数料は5万円です。このほか、謄本代で2000円程かかります。
(設立全体にかかる費用については➡一般社団法人の設立にかかる費用 )
(一般社団法人設立全体の流れについては➡一般社団法人設立の流れ)
一般社団法人の定款に必ず記載しなければいけない内容
ここからは、先ほどの『2 定款内容を決める』について、より詳しく解説します。
最初に一般社団法人の定款に必ず記載の必要な事項(絶対的記載事項)について解説します。
1 目 的
目的とは、一般社団法人が行う事業のことです。
単に事業内容を列挙するだけでも問題ありませんが、次のように、最初に抽象的な法人の目的を書いて、続けて具体的な事業内容を列挙するのが一般的です。
第●条 当法人は、〇〇〇〇することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1 〇〇〇〇
2 〇〇〇〇
3 その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(目的の詳細については➡一般社団法人の定款に記載する目的の記載方法と注意点)
2 名 称
一般社団法人の名前です。
名称中に必ず一般社団法人という文字を使用しなければなりません(語頭でも語尾でもOK)。
登記手続き上は、同一住所に同一名称の法人が存在しない限り、登記がとおります。
しかし、不正の目的をもって、他の法人と誤認されるおそれのある名称等をしようすることは法律で禁じられているので注意しましょう。
名称の決定をする際には、国税庁の法人番号公表サイトを利用して名称調査をしておくとよいです。
(名称の詳細については➡一般社団法人の名称の決め方|ルール・注意点・便利な調査方法 )
3 主たる事務所の所在地
主たる事務所とは、一般社団法人の住所のことです。
定款に定める主たる事務所の所在地は、市区町村までの特定でOKです。
4 設立時社員の氏名又は名称及び住所
設立時社員の氏名又は名称及び住所は、設立時に作成する定款に必ず記載します。
法人の設立後は、社員に変更があっても定款を書き換える必要はありません(設立後は社員名簿で管理しましょう)
5 社員の資格の得喪
どのようにして社員の資格を得て、社員資格を喪失するかについての定めです。
6 公告方法
一般社団法人の公告方法には、次の4種類があります。
- 官報に掲載する方法
- 日刊新聞紙に掲載する方法
- 電子公告
- 主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法
主に、どのような方法で決算公告をするのかという基準で選びます。
電子公告を選ぶ場合は、URLを登記する必要があるので、設立登記申請時までに電子公告を掲載するURLの準備が必要になります。
また、電子公告を選ぶ場合は、電子公告ができない事態に備えて、「ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。 」と併せて併記するのが一般的です。
7 事業年度
一般社団法人の会計年度です。
会計年度の末日を決算日といいます。
個人事業主とは異なり、決算日は自由に選択することができます。
初年度が1年を超えないよう注意して定めましょう。
一般社団法人の定款に定めなければ効力の生じない内容
次に、制度を利用するためにはその旨を一般社団法人の定款に記載しなければならない事項(相対的記載事項)の一部について解説します。
機関設計に関するもの
一般社団法人の必置機関は、次の2つのみです。
- 社員総会
- (代表)理事
上記の2つの機関は、定款への記載がなくとも必ず一般社団法人に置かれます。
そして定款で定めることで置くことができる機関は次の3つがあります。
- 監事
- 理事会
- 会計監査人
会計監査人を置くケースは稀(200億円以上の負債がある大規模一般社団法人の場合に置かなければならない)なので、本コラムでは省略します。
1の監事は単体で置くことができます(社員総会、理事、監事という設計はある)。
2の理事会を置く場合、必ず監事を置かなければいけません。
したがって理事会を設置する場合は必然的に社員総会、理事、理事会、監事という機関設計になります。
理事会を置く場合は、監事を含めて役員が必ず4人以上必要ということをおさえておきましょう。
(関連記事➡一般社団法人の理事会設置の検討は慎重に)
(関連記事➡一般社団法人の理事会廃止の手続き及び費用)
経費の負担(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」)27条)
社員に経費の支払義務を負わせるには、定款にその定めを置くことが必要とされています。
具体的には次のような記載です。
“(経費等の負担)
第●条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。”
一般社団法人には資本金の概念のないので、設立当初は社員が経費を負担するケースが少なくありません。このような場合には、この規定を置くようにしましょう。
任意退社に関する別段の定め(一般法人法28条)
社員は、いつでも退社することができるのが原則です。
しかし、定款で定めることによって別段の定めをすることができます。
別段の定めとしては、
“ただし、●か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。”
などと定めることが多いです。
なお、この定めを設けた場合でも、退社する社員にやむを得ない事由があるときは、社員はいつでも退社することができます。
法定退社の事由(一般法人法29条1号)
法定退社とは、社員自らの意思とは関係なく、法律上定められた事由の発生により、社員が当然にその地位を失い、退社することです。
法定退社事由には、総社員の同意、死亡又は解散、除名のほか、定款で定めた事由の発生があります。
この定款の定めとしてよく見かけるのが、
“(社員に会費を支払う定めがある場合に)〇年以上会費を滞納したとき”
というものです。
電子提供措置をとる旨の定め(一般法人法47条の2)
電子提供措置とは、社員総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、社員に対し、そのウェブサイトのアドレス等を書面により通知することによって、社員総会資料を提供することができる制度です。
この制度を利用するには、定款にその定めを設ける必要があります。
具体的には、次のように定めます。
“(電子提供措置)
第●条 当法人は、社員総会の招集に際し、社員総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。”
社員総会の議決権の数に関する別段の定め(一般法人法48条)
社員は、社員総会で原則1人1議決権を有します。
定款で定めることで、社員ごとに議決権数に差をつけることができます。
なお、公益社団法人では、議決権についての差別的な取り扱い、各社員が法人に対して提供した金銭その他の財産に応じた異なる取り扱いが禁止されています。
(関連記事➡一般社団法人の社員総会の議決権について)
定足数に関する別段の定め(一般法人法49条)
社員総会の普通決議は、
“総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。”のが原則です。
定款で定めることによって、普通決議の定足数を撤廃することができます。
定足数を撤廃する場合は、次のように定めます。
“社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。”
なお、公益社団法人では、定足数の緩和は一定の制限を受けます。
役員の任期に関する定め(一般法人法66条、67条)
理事と監事の任期の原則はそれぞれ次のとおりです。
理事:選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで。
監事:選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで。
任期の伸長はできません(理事及び監事共通)。
理事の任期の短縮は自由にすることができます。
監事の任期の短縮は次の2パターンのみ可能です。
- 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までを限度として短縮
- 補欠として選任された監事の任期を前任者の任期満了時までとする
理事の任期短縮については、定款の定めまたは社員総会の決議によって行うことができますが、監事の任期短縮は必ず定款の定めによっておこないます。
(関連記事➡一般社団法人の役員任期切れていませんか?)
代表理事及び業務執行理事の理事会への自己の職務執行状況の報告に関する定め(一般法人法91条2項)
理事会を設置する一般社団法人では、代表理事・業務執行理事は、原則3か月に1回以上のペースで自己の職務執行状況を理事会へ報告しなければなりません。これは実際に理事会を開催して報告を行う必要があります。
しかし、定款で次のように定めることで、その報告頻度を緩和することができます。
“代表理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告をしなければならない”
理事会議事録への署名又は記名押印義務者に関する規定(一般法人法95条3項)
一般社団法人の理事会議事録には原則として、理事会へ出席した理事と監事の全員が、署名し、又は記名押印をしなければなりません。
しかし、定款で定めることで署名又は記名押印義務者を、理事会へ出席した代表理事及び監事に限定することができます。
理事の人数が多い法人の場合、全理事から署名や押印を集めるのは骨が折れる作業です。
この規定を置くことで、その作業量を緩和することができます。
具体的には次のように記載します。
“(議事録)
第●条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。”
理事会の決議省略に関する定め(一般法人法第96条)
理事会の決議は、実際に理事会を開催をして行うのが原則です。
しかし、定款に「理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす」旨を定めている場合は、理事会を実開催せずに決議を行うことができます。
具体的には次のように定めましょう。
“(決議)
第●条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。”
理事等による損害賠償責任の一部免除に関する定め(114条1項)及び責任限定契約に関する定め(115条1項)
一般法人法111条1項より、理事、監事又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。
この損害賠償責任は、総社員の同意がないかぎりは、完全に免除することはできません。
しかし、一般法人法114条1項の定款の定めを置いている法人では所定の機関で決議がなされることにより、これを一部免除することができます。
また、115条1項の定款の定めを置いている法人ではその契約内容に基づいて一部免除することができます。
定款規定を置く場合は、それぞれ次のように定めます。
“(責任の一部免除又は限定)
第●条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、金〇万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。”
一般法人法114条1項の定款規定は理事会を設置しない一般法人でも設定することができますが、次の要件をいずれも満たしている必要があります。
- 監事設置一般社団法人であること
- 理事が2名以上いること
理事会を置かない一般社団法人で114条1項の規定を設ける場合は、「理事会の決議により」とあるところを「理事の過半数の同意により」に置き換えましょう。
なお、113条1項の規定により、社員総会の特別決議によって一部免除することもできますが、こちらは定款の定めは不要です。
基金に関する定め(一般法人法131条)
基金は、一般社団法人の資金調達方法の一つです。
基金の制度を利用するためには、定款にその定めを設ける必要があります。
非営利型一般社団法人のうち非営利性が徹底された法人として設立する場合の定款規定
次の2つの定款規定を必ず設ける必要があります。
- 剰余金の分配を行わないこと
- 解散したときはその残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与すること
具体的には次のとおりです。
“(剰余金の不分配)
第●条 当法人は、剰余金の分配を行わない。”
“(残余財産の帰属)
第●条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第20号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。”
また、非営利性が徹底された一般社団法人では、「各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。」という要件があります。
こちらは定款への記載までは求められていないものの、これを強調する意味で次のような規定が置かれていることが一般的です。
“各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。”
(関連記事➡非営利型の一般社団法人とは?メリットと要件)
まとめ
今回のコラムでは、一般社団法人の設立時の定款作成についてご紹介しました。
一般社団法人の設立時は、定款作成について注意しなければならない点が多々あります。
設立時に対応した士業や無資格コンサルから適切なアドバイスを受けられなかったために、
「非営利型の要件を満たしていないまま設立してしまった」
「想定していた機関設計で設立ができておらず設立後に余計な手間や費用が発生してしまった」
という方からのご相談は本当に頻繁にあるものです。
一般社団法人専門の税理士さんと共著で執筆したこちらの本では、定款作成についてさらに詳しく解説しています。ぜひお読みいただければ幸いです。
「一般社団法人設立・登記・運営がまとめてわかる本(日本法令)」
一般社団法人の設立をご検討中の方へ
一般社団法人は設立時の定款設計が非常に重要です。
本来設立する法人の事業内容や運営方法に合わせてオーダーメイドで作成されるべきものですが、一般社団法人に詳しい専門家が少ないことから、ネットに落ちている雛型で取り敢えずの定款が作成されてしまうケースが少なくありません。
このようなケースでは、法人の設立後に思わぬ手間や費用がかかってしまうことが非常に多いです。最悪の場合は、法人を乗っ取られてしまうというリスクもあります。
弊所は、一般社団法人の設立手続きに専門特化した司法書士事務所です。これまでに数百社の一般社団法人の設立手続きを対応していますので、安心してご相談ください。初回のご相談は無料です。オンラインで全国からのご相談に対応しています。
📌 あわせて読みたい関連記事
【設立関連コラム】
- 一般社団法人の設立を考えたら最初に読むページ
- 一般社団法人の設立|人数・費用・必要書類・流れ・期間・定款
- 一般社団法人設立時の必要書類を司法書士が徹底解説
- 一般社団法人設立の流れ
- 一般社団法人の設立にかかる費用
- 一般社団法人の設立に必要な人数をケース別に解説
- 非営利型の一般社団法人とは?メリットと要件
- 土日・祝日・年末年始も一般社団法人の設立日にできるようになりました!
- 一般社団法人の設立、誰に相談するのが正解?
- 一般社団法人の役員氏名に旧姓を併記するには?
- 一般社団法人で利用できる代表理事の住所非表示措置について
- 一般社団法人の主たる事務所の表記方法
- 実質一人社員で一般社団法人を設立する方法
- 一般社団法人の理事会設置の検討は慎重に
- 一般社団法人の「社員」とは?
- 任意団体から一般社団法人へ|信用力アップ・寄付金獲得のための法人化ガイド
- 一般社団法人の設立に必要な最低人数
【運営関連コラム】
📘 著書(共著)
「一般社団法人設立・登記・運営がまとめてわかる本(日本法令)」